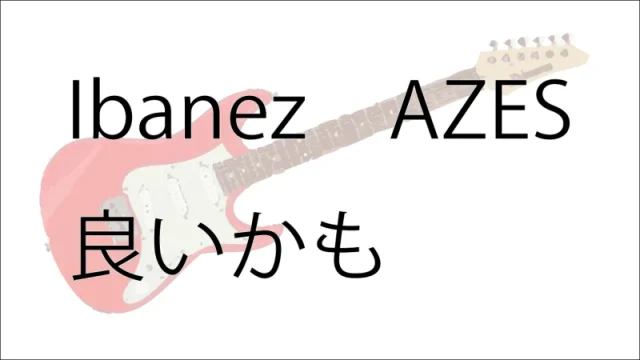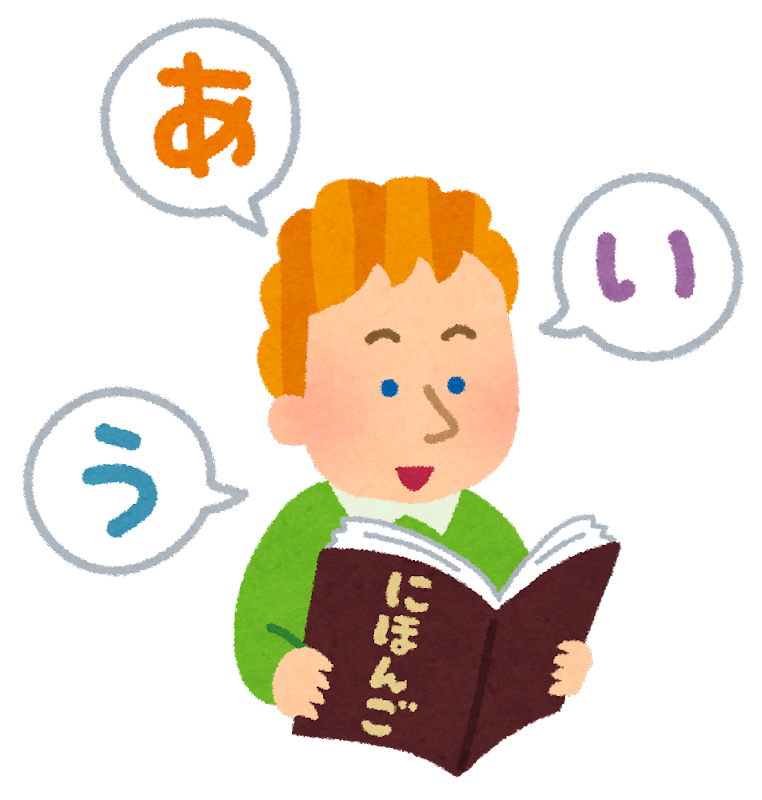歪みエフェクター初心者ガイド|使い方・仕組み・種類・おすすめモデルまで徹底解説
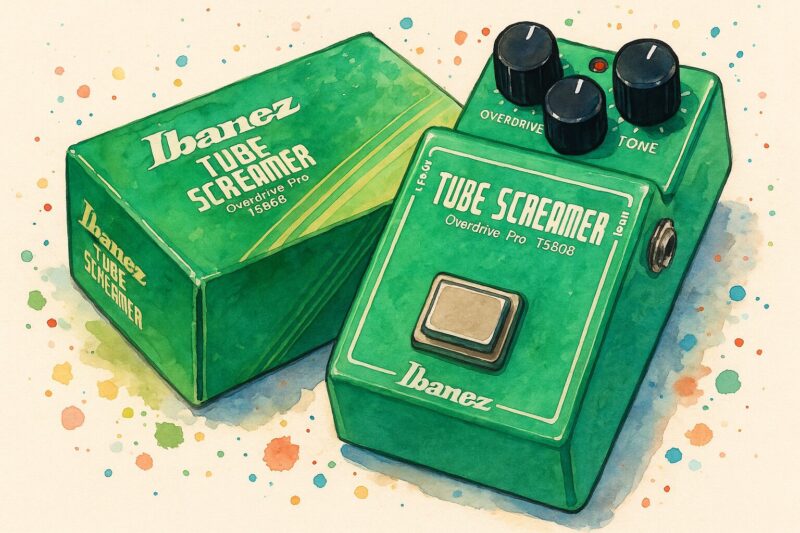
「歪みエフェクターって、結局どう使えばいいの?」
ギターを始めたばかりの人も、経験者も、一度はこう思ったことがあるはず。音作りの核になるエフェクターだけに、選び方や使い方で悩むのは当然だ。
結論から言えば、歪みエフェクターはただ「歪ませるだけ」の道具じゃない。
音のキャラクターづくりから音量調整、果てはノイズ対策まで、その用途は多岐にわたる。
この記事では、そんな歪みエフェクターの代表的な使い方5選に加え、意外と知られていない使い方や仕組み、種類、初心者向けおすすめモデルまでを一気に解説する。
ギター初心者にも、中級者にも、きっと新しい発見があるはずだ。
歪みエフェクターの使い方5選

1. メインの音作り
アンプはクリーンのまま、エフェクターで歪みを作るというのが定番スタイル。
クリーンから歪みへスイッチひと踏みで瞬時に切り替えれるのが便利。
エフェクター自身の個性がはっきりと出る為、音作りの「軸」として使われることが多い。
2. プリブースター
アンプや次のエフェクターに入る前の信号をブースト。
これによってより激しい歪みやサステインを得られる。ソロで勢いを出したいときなどに重宝する。
エフェクターのキャラクターが出にくい使い方でもある。
3. ポストブースター
歪みエフェクターの後段やアンプのセンドリターンに配置し、音量を上げる用途で使用。
ソロやフレーズの前に「一歩前に出る」ための役割を持つ。
アンプが歪んでいてもクリーンでも音量を上げる事ができる。
プリブースターよりもエフェクターのキャラクターが影響しやすい。
4. リデューサー(減衰)
LEVELつまみを使ってアンプへの入力音量を意図的に下げることで、暴れすぎるサウンドを制御。高出力アンプの扱いが難しいと感じている人におすすめ。
ナンバーガールの田渕ひさ子さんが実践していることで有名だが、荒々しいアンプサウンドをコントロールしたい時に便利。
5. 音色補正
トーンやEQを活用して、歪みの出方や帯域を調整したりエフェクターのキャラクターだけを付与するような使い方。バンド全体の中でギターが浮きすぎたり埋もれたりするのを防ぐ。
歪みエフェクターのその他の使い方

ミュートスイッチ代用
LEVELを0にしておけば、オンにしたときだけ音が消える。ギターの交換時などライブで瞬間的に音を切るときなどに有効。
飛び道具として使う
ゲインやトーンを極端に振ったセッティングで、ノイズ音やこもった音、金属的なサウンドを作る。エフェクティブな演出が必要なときに活躍。
バッファ用途
ボードの先頭に置くことで、信号をローインピーダンスに変換。長いシールド使用時の劣化やノイズを防ぐ役割も果たせる。

歪みエフェクターの仕組み

ゲイン(GAIN):信号を増幅し、歪みの量を決めるセクション。
ここで増幅された信号は波形がクリップ(潰れる)され、歪んだ音になる。つまり、ゲインを上げれば上げるほど、歪み量が増し、サステイン(音の伸び)も長くなる。
逆にゲインを下げればクリーン寄りになるので、アンプや他のエフェクターと組み合わせるときの重要なコントロールだ。
トーン(TONE):音色の高域や低域を調整。
たとえば高域を持ち上げれば抜けの良い派手な音に、低域を強調すれば太く厚みのある音になる。
逆に高域を下げると角が取れてマイルドなサウンドに、低域を抑えるとタイトな音になる。アンプやバンド全体の音作りに馴染ませる際に、とても役立つ。
ツマミ一つで高域から低域までをトータルでコントロールできるものもあれば
HIGH、MID、LOWなど帯域ごとにコントロールできるものもある。レベル(LEVEL):エフェクターから出力される信号の音量をコントロールする。
ゲインが歪み量を決めるのに対し、レベルは音量を決める。ゲインを上げすぎると音量が上がりすぎたり、逆に下げると小さくなるので、最終的な音量をここで調整することで、バランスの取れたサウンドが作れる。
特にライブやリハでは「踏んだら音がデカすぎ!」なんてことを防ぐために必須の調整だ。
この3つのコントロールを調整して音作りしていく。
歪みエフェクターの種類とその違い

オーバードライブ
アンプの自然な歪みを模したナチュラルな歪みが特徴。
音の輪郭が保たれたまま、暖かく、粘りのある歪みを得られる。
仕組みとしては、入力信号を緩やかにクリッピング(波形を丸める)し、倍音を加えることで自然な歪みを作り出す。
ブルースやポップス、ロックのクランチサウンドにぴったりだ。


ディストーション
オーバードライブよりも強く歪ませるタイプ。
より激しく、鋭く、厚みのある音を作れる。
仕組みとしては、信号をハードクリッピング(波形を鋭くカット)して、派手な倍音と強烈なサステインを生み出す。
ハードロック、メタル、パンクなど、パンチが求められるジャンルで主役になることが多い。
ファズ
1960年代から愛される独特の「潰れたような」歪みが特徴。
ゲルマニウムやシリコンなどのトランジスタを使って信号を過激に歪ませ、矩形波に近い荒々しい波形を作る。
まさに破壊的なサウンドで、ジミ・ヘンドリクスやスマッシング・パンプキンズが愛用したことで有名だ。ファズだけが持つ「暴れ感」は唯一無二。
初心者におすすめのモデル
■ BOSS OD-3(オーバードライブ)
扱いやすくて、歪み量も十分。オーバードライブの醍醐味が味わえる1台。


■ Proco RAT2(ディストーション)
ジャンルを問わず使える万能ディストーション。荒々しいサウンドが特徴。

■ Electro-Harmonix BIG MUFF(ファズ)
シンプルな操作性と圧倒的なサステイン、ファズの入門機として最適。

ELECTRO-HARMONIX ( エレクトロハーモニックス ) / BIG MUFF PI

Q&A:この記事の振り返り
Q:歪みエフェクターって何に使うの?
A:主に音作り、ブースト、補正など多目的に使えます。
Q:オーバードライブとディストーションの違いは?
A:歪みの強さとキャラクター。オーバードライブはナチュラル、ディストーションは攻撃的。
Q:初心者におすすめの1台は?
A:ジャンルに迷っているならBOSS OD-3。使いやすさで人気です。
Q:トーンやゲインの調整が難しい…
A:まずは12時方向(ノブを真ん中)から始めて、耳で確かめながら少しずつ調整しましょう。
最後に:これからもギターにまつわる情報を発信していきます
この記事では、歪みエフェクターの使い方や仕組み、種類、選び方について解説してきた。
歪みエフェクターは奥が深く、知れば知るほど音作りが面白くなるパーツの一つ。
GAINMAGでは、今後もエフェクターをはじめ、ギターライフを豊かにするさまざまな視点から情報を発信していく予定。
ギターともっと仲良くなりたいあなたのために、これからも役立つコンテンツを届けていきます。