【島村楽器】HISTORYの評判と実力|ダサいと言われてもおススメできる理由

「名前がダサい」「店員の押し売りがすごい」──そんな評判で知られるギターブランド、HISTORY(ヒストリー)。
ネット上では何かとネタにされがちですが、実際のところ、その品質と完成度は想像以上に高いものです。
どうも、7丁目ギター教室新潟江南校の吉田です。
この記事を読めば、なぜHISTORYが「地味だけど良いギター」と評価されるのか、そして中古市場でなぜ今こそ狙い目なのか、その理由がハッキリと分かるはずです。
HISTORYとは
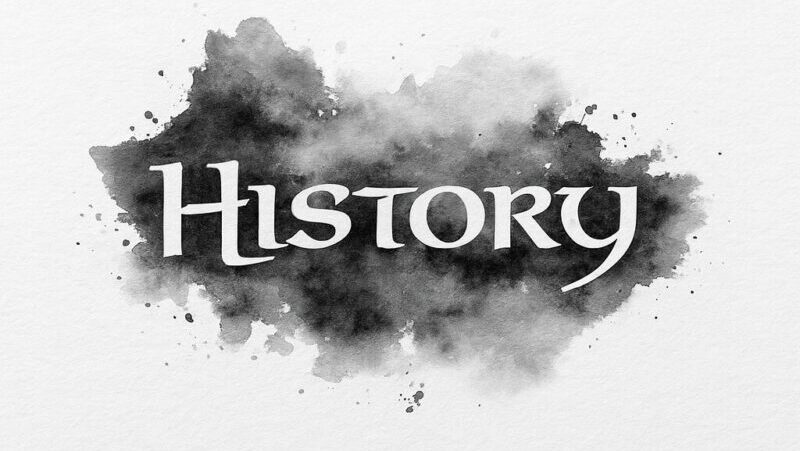
HISTORY(ヒストリー)は、皆さんも一度は行ったことがあるであろう楽器店「島村楽器」が展開するオリジナルの国産ギターブランドです。
1990年代後半から展開され、製造は日本屈指のギターファクトリーである「フジゲン(FUJIGEN)」や「ダイナ楽器」が担当しています。
量産モデルでありながら、出荷前に全数検品や徹底したセットアップが行われているのが大きな特徴で、国産ブランドの中でも品質の安定性は群を抜いています。
また、全体的にクセの少ない設計思想で作られており、どんなジャンルにも対応できる「万能型ギター」としても知られていますね。
ギター仲間や生徒さんがHISTORYを持っていると、調整がしっかりされていることが多い印象。
木の状態が動きにくかったり、新品時点でのセッティングがある程度追い込まれていたり、細かい部分に職人的な気配りを感じますね。
サークル・フレッティング・システムとは
フジゲン製HISTORYの代名詞的な技術であり、最大の特徴が「サークル・フレッティング・システム(Circle Fretting System / C.F.S.)」です。
通常のギターは、フレットがネックに対して直線的に打たれています。
一方、C.F.S.ではフレットをわずかに円弧状(サークル状)に打ち込むという特殊な構造になっています。
この設計によって、弦とフレットの接地角度がすべての弦で垂直に近づき、
結果として以下のようなメリットが生まれます。
各弦・各ポジションでのピッチ(音程)の安定性が向上
コードを鳴らしたときの濁りが減少し、響きがクリアになる
サスティン(音の伸び)と音抜けが改善される
実際、レコーディング現場などで「コードの響きが揃いやすい」という理由で採用しているプロプレイヤーも多いです。
一方で「効果が分かりにくい」「プラシーボ(思い込み)では?」という意見もあり、プレイヤーの感覚や好みによって評価が分かれる技術でもあります。
ちなみに自分も以前、フジゲンのプライベートブランドであるFGNのギターを所有していましたが、それにもサークルフレットが採用されていました。
実感としてコードの響きはかなり安定していましたし、それと比較してUSA製のFenderなどは、オクターブピッチを合わせていてもややルーズかつワイルドな響きに感じました。
一度フジゲン製の楽器に慣れてしまうと、他社製の楽器はピッチがやや甘く感じてしまうほどです。
良くも悪くも「プレイヤーの耳を厳しく鍛えてしまう楽器」と言えるかもしれませんね。
HISTORYの強みはコスパと安定性

特に新品価格で10万円を超えるグレードになると、品質は国産ブランドの中でもトップクラスです。
同価格帯の日本製FenderやEpiphoneなどと比べても、いわゆる「外れ個体」を引くリスクが極めて少ないのが魅力です。
HISTORYの上位モデルは、フジゲン(FUJIGEN)によって製造されています。
フジゲンといえば、Ibanezの最高級ライン(j.custom等)を製造していることでも有名ですが、過去にはG&Lのプレミアムシリーズ、MUSICMANのEXシリーズ、そしてFender Japanの製造も担当していた、まさに「伝説の老舗メーカー」です。
日本国内でも最高峰の生産技術を持ち、木材の乾燥管理から組み込み精度、最終セットアップの丁寧さは世界的に見ても高水準です。
その技術がHISTORYにも惜しみなく注がれています。
フジゲン製モデルに採用されるサークル・フレッティング・システム(C.F.S.)のおかげか、ピッチが安定していてレコーディングでも非常に扱いやすい。
さらにフレットの端の処理やネックの安定性も高く、日本の四季による湿度変化の中でもトラブルが少ない印象です。
新品はもちろん、中古市場でも「10万円以上のモデルで外れを見たことがない」という声は少なくありません。これは中古購入において非常に大きなアドバンテージです。
弾きやすさへの徹底したこだわり
HISTORYの上位機種では「エリートフィニッシュ」と呼ばれるフレット端の球面処理が施されており、運指のスムーズさは驚くほどです。指に引っかかる感じが全くありません。
また、ネックシェイプはローポジションからハイポジションにかけて握り心地が自然に変化する独自設計を採用しているモデルもあり、どのポジションでも無理なく演奏できます。
こうした「弾き手がストレスを感じない」細部への気配りが、初心者にもプロにも「弾きやすい」と言われる所以でしょう。
音のキャラクター|万能さゆえの物足りなさ
サウンドの傾向としては「艶がある」「整っていて万能」という評価が多いです。
どんなアンプやエフェクターとも相性が良く、スッと馴染むので、スタジオミュージシャンやサポートギタリストには強い味方になるはずです。
一方で、個性が強烈にあるわけではないので「優等生すぎて面白みがない」と感じる人もいるでしょう。
USA製ギターのような暴れるような倍音や、ビンテージ特有の「扱いづらいけど良い音」を求める人には、少々物足りなく感じるかもしれません。
まさに「クラスに一人はいる、何でもできるけど印象に残りにくい優等生」ってな感じですね。
高コスパの理由を考えてみる
HISTORYのギターが「価格以上の品質」と言われる理由は、単に工場の腕が良いからだけではありません。
背景を少し掘り下げてみると、構造的にコスパを高める要素がいくつも存在しているのです。
1. 島村楽器のプライベートブランドであること
まず大きなポイントは、HISTORYが**島村楽器のプライベートブランド(自社ブランド)**であるということ。
通常、FenderやGibsonなどの有名ブランドのロゴを付けるには、莫大なブランド使用料や広告費が価格に乗ってきますが、HISTORYにはそれが必要ありません。
つまり、宣伝やブランドライセンスにかかる余計なコストを省ける構造になっています。
浮いたコストがそのまま「良い木材」「良いパーツ」「丁寧な組み込み」に還元されているため、同価格帯の他社製品よりも作りが良いと感じる人が多いのも納得です。
2. 型数を絞った効率的なラインナップ
HISTORYは基本的にトラッドなモデル(ストラト、テレキャス、レスポール、ベース等)を中心に展開しており、極端な変形モデルや複雑な仕様は少ないです。
型番が違っても、同グレード内ではボディ形状やネックの設計が共有になっているケースが多いです。
この仕様統一によって製造ラインの効率が上がり、結果としてコストを抑えながら品質を維持することが可能になっています。
シンプルなモデル構成が、安定供給と優れた価格バランスを支えているわけです。
3. 圧倒的な店舗数によるスケールメリット
島村楽器は全国に180店舗以上を展開する国内最大級の楽器チェーンです。
当然、各店舗にHISTORYのギターが並ぶため、メーカー(工場)への発注数そのものが膨大になります。
製造を請け負うフジゲンやダイナ楽器も自社ブランドを持っていますが、HISTORY向けの受注数は桁違いでしょう。
その規模ゆえ、**大量生産によるスケールメリット(量産効果)**が働き、結果的に1本あたりの製造コストを下げることができます。
もしかすると、工場の自社ブランド(FGNなど)と同等、あるいはそれ以上のコストパフォーマンスを実現している可能性すらあります。
少なくとも「割高なブランド」ではないことは間違いありません。
4. 円安の中でも価格が安定している
最後に、為替の影響を受けにくい構造もHISTORYの強みです。
FenderやGibsonといった海外ブランドは、円安が進むたびに輸入コストが増え、価格がどんどん上昇しています。
その点、HISTORYは国内生産・国内販売・商社を介さない流通で完結しており、中間マージンや為替リスクがほとんどありません。
だからこそ、近年の歴史的な円安局面でも価格が比較的安定しています。
この「価格が上がりにくい構造」こそ、HISTORYが長年“高コスパブランド”として評価され続けている理由の一つでしょう。
中古も狙い目

実は、中古のHISTORYは非常に狙い目です。
「名前がダサい」「店員の押し売りが…」といったネガティブなイメージが先行している影響で、ブランド力のあるGibsonなどに比べて中古価格はかなり安く落ち着いています。
ものによっては定価から10万円以上安く販売されているケースも珍しくありません。
もともと品質管理の精度が高いため、中古でもネックの状態が良い個体が多く、経年による致命的なトラブル(ネックのねじれ等)のリスクも少ないのが嬉しいポイント。
この価格帯でこれほど安心して買えるブランドはなかなかないですね。
実用性を重視するなら、中古市場においてHISTORYのコストパフォーマンスに対抗できるブランドはほとんど存在しないと言っていいでしょう。
逆に考えると、売却時の価格(リセールバリュー)も安くなる傾向があるため、投資商品的な価値は低いです。「買って、弾き倒して、使い潰す」ための、長く愛用すべきギターです。
個人的な狙い目は、中古市場で10万円前後で取引されているレスポールタイプ(GH-LCなど)です。
本家Gibsonなら30万円以上出さないと得られないようなクオリティを、その価格で手に入れられる個体が多いですよ。
湖底の古木
中古を探す際に、ぜひ確認してほしい「ロマンあふれる」ポイントがあります。
それがヘッド裏の刻印表示です。
もし「Heritage Wood」「Timeless Timber」「Aqua Timber」といったロゴが入っていれば、それは大当たり。
これらは、大昔に伐採された木材が輸送中に湖に沈み、そのまま長期間、空気の遮断された冷たい湖底に眠っていたものを引き上げて乾燥させた貴重な古木材が使用されている証です。
この木材は、伐採当時で樹齢200年以上、さらに湖底で70〜250年もの時間を過ごしてきたといわれます。
長い年月を経て木材の中の不純物が抜け、細胞壁が結晶化することで密度が高まり、振動伝達の良い理想的なトーンウッドになっています。
実際、この材を使用したモデルは倍音が豊かで、芯のある艶やかな響きを持つと評判です。
まさしく「History(歴史)」の名にふさわしい、時を超えたロマンを感じられる一本。見つけたらぜひ弾いてみてください。
エントリークラスのPerformanceシリーズ
さて、現行のHISTORYの中でも、もっとも身近なラインがPerformanceシリーズです。
製造を海外(主に中国など)にすることで価格を抑えつつも、国内で厳しい品質管理を行うことで「弾きやすさ」と「信頼性」を両立したモデル。これからギターを始める人の「最初の1本」として非常に優秀です。
弾きやすさ重視の設計
ネックはCシェイプとUシェイプの中間のような形状で、誰の手にも自然になじむグリップ感です。
さらさらとしたマット仕上げ(サテンフィニッシュ)のため、手汗をかいて長時間弾いても手に張りつかず、滑らかにポジション移動ができます。
特に注目したいのが、フレットの両端を丸めたラウンドエッジ仕様。安価なギターによくある「フレットがチクチクして痛い」ということがありません。
さらにハイポジション(高い音)の演奏を快適にする、接合部を薄くカットしたEasy Accessジョイント構造も採用しており、上達しても長く使えます。
サウンドの幅も広い
専用開発のピックアップにより、透き通ったクリーンから激しいロックサウンドまで幅広く対応できます。
HST(ストラトタイプ)ではブレンダーノブを回すことでシングルコイル~ハムバッカーのような太い音まで無段階で作れます。
HTL(テレキャスタイプ)はプッシュ/プル式スイッチで出力を切り替えられ、ギターソロの時だけ音を太くする、なんてことも可能です。
長く使える安心設計
個人的に一番評価したいのがここ。ジャック部(シールドを挿す穴)に緩み止めのノルトロックワッシャーを採用している点です。
初心者のトラブルNo.1である「ジャックの緩みによる断線」を未然に防いでくれます。
保証期間も3年間と長めで、全国の島村楽器でサポートを受けられるのも強み。
肉厚なクッションが入った専用ギグバッグも標準で付いてきます。
手に取りやすい価格帯
価格はおおよそ8〜9万円台(税込)。 中古だと5~7万円程度で取引されています。
海外工場製とはいえ、設計・品質管理は国内基準で行われているので、コストを抑えながらも作りはしっかりしています。
「初めてのエレキを買うけど、すぐ壊れる安物は嫌だ」「2本目に信頼できるサブギターを持ちたい」──
そんなプレイヤーにとって、最初の“本格的なエレキギター”として胸を張っておすすめできるシリーズです。





まとめ|「ダサい」名前の裏に隠れた堅実さ

HISTORYは派手さやブランドイメージで勝負するメーカーではありません。
むしろ「安心して弾けるギター」「絶対に外れを引きたくない人向けのギター」として独自の価値を持っています。
現在は~10万円位のモデルはダイナ楽器、上位モデルはフジゲンが製造を担当しており、いずれも高品質で同価格帯の楽器に引けを取ることはまず無いでしょう。
名前がダサいとか、押し売りがすごいとか、そんなネタで語られることも多いですが──実際に手にした時に感じる安定感や安心感は、本当に大きなものです。
「変に尖った個性は要らない、安定して良い音を出してくれる仕事道具が欲しい」という人には、間違いなく勧められるブランドだと思います。
ブランドロゴだけで判断して食わず嫌いするのはもったいない、ってな感じですね。
島村楽器に立ち寄った際は、店員さんの押し売り覚悟で(笑)、ぜひ一度試奏してみてください。
おまけ

↓要約ソング




