「下手でも気持ちがこもっていればOK」は本当か? ギター演奏に必要な視点

ギターをやっていると、一度は耳にする「テクニックが大事か、それともハートか?」という問い。上手いだけじゃ伝わらない、心がこもってなきゃ意味がない──そんな言葉もよく聞く。
でも、この議論、どこかズレていないか?
「ブルースとメタル、どっちが偉いか?」といったジャンル間の論争と同じで、そもそも比べること自体がナンセンスだ。
「ハート」とは何か?
ここで言う「ハート」は、単なる感情ではない。演奏に対する情熱、音に込められた感情、そして表現者としての魂。それらをひとまとめにした、“心のエネルギー”のようなものだ。言い換えれば、「自分の演奏で何かを伝えたい」という気持ちの総体である。
なぜ「テクニック vs ハート」は対立構造になるのか?
この対立がなぜ起きるのか。その背景には、実は感情的なものが大きく関わっている。
テクニック派は、自らの努力に誇りを持っている。積み上げた練習時間や習得した演奏スキルが、ただの「気持ち」で評価されてしまうことに、どこかモヤモヤしたものを感じている。荒削りなパンクやインディーズの音楽が“かっこいい”と称賛されるのを見て、「もっと練習してくれよ」と言いたくなる気持ちもわかる。
一方、ハート派には、テクニックへの劣等感がにじむことがある。「上手くはないけど気持ちはある」という主張は、届かない技術への嫉妬からくる防衛反応に近いときもある。ブルースやパンクロックの“技術よりも魂”という美学を拠りどころにして、技術のハードルを回避しようとする動きも見える。
結局ぶつかっているのは主張じゃなくて、「立場」なのだ。
テクニックとハートは対立していない
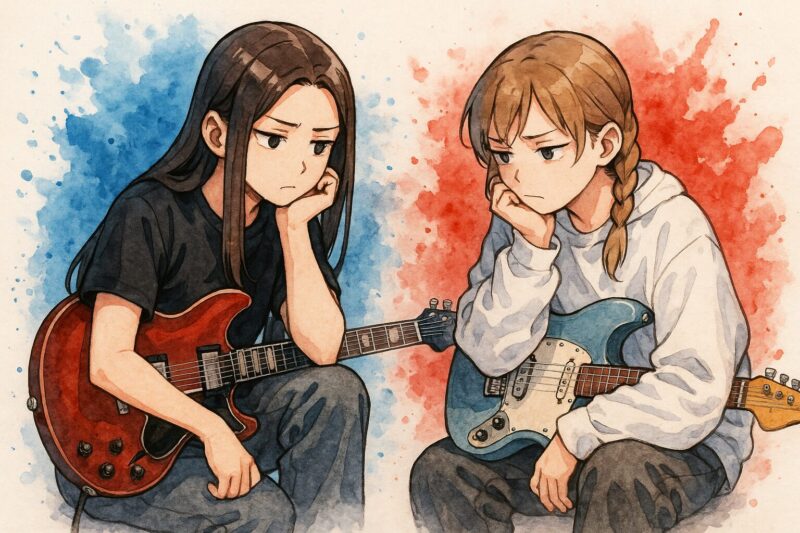
本来、テクニックとハートは敵対するものではない。むしろ、支え合ってこそ意味を持つ。
心を込めたくても、それを音にできる技術がなければ、想いは空回りする。逆に、どれだけ技術があっても、そこに気持ちがなければ、ただの器用な演奏で終わる。
ブルースはハートだけか?
ブルースは「感じる音楽」とよく言われる。確かに、感情の乗ったチョーキングやビブラートは聴く者の心を打つ。でも、それを成立させるのは、繊細なコントロール技術だ。
タイミングの“間”、ピッキングの強弱、フレーズの選び方。どれも熟練があってこそ初めて光る。心を込めることは、それを支える技術があるから可能になる。
メタルはテクニックだけか?
一方のメタルは、高度なテクニックの象徴として語られることが多い。超速のピッキング、タッピング、変拍子に対応したリフ。それらは確かに圧巻だ。
だが、それらを身につけるには、並大抵の情熱では続かない。音数が多くなればなるほど、込めるべき“気持ち”のコントロールも難しくなる。メタルにもまた、魂が宿っていなければ成り立たない。
初心者が陥りやすい「ハート信仰」の罠
特に初心者に多いのが、「気持ちがあれば伝わる」という考え方。だが現実には、最低限の演奏力がなければ何も伝わらない。
コードがまともに押さえられず、リズムもズレていたら、聴く側にはストレスになる。どれだけ熱い思いがあっても、届ける力がなければただの独りよがりで終わる。
想いを“伝える”ためには、まず音に乗せる技術がいる。
テクニック偏重のSNS時代、その功罪
現代ではSNSによって、「目を引くテクニック」がバズる時代になった。速弾き動画や派手なトリックプレイが注目されやすいのは、映像のインパクトが大きいからだ。
ただ、それに偏りすぎると“見せる演奏”ばかりが先行し、“伝える音楽”が置き去りになることがある。技術を魅せることが目的になってしまえば、表現としての深みは失われる。
こういう時代だからこそ、演奏の“中身”が問われる。
「我が子の発表会」現象をどう捉えるか
下手でも感動する演奏がある。それはたいてい、演奏者に対して思い入れがある場合だ。応援している人、頑張っている姿を知っている人。そういった“背景”があるからこそ、心が動く。
我が子の発表会や運動会を想像してみれば分かりやすい。
だが、それは親しみがあるから成立する感動だ。見知らぬ人の心に届けるには、技術という媒介が必要になる。
ギターは「心技一体」でこそ輝く
ギターという楽器は、技術だけでも、気持ちだけでも成立しない。どちらかが欠ければ、伝わる音にはならない。
練習するのは、想いをもっと自由に乗せるため。心を込めるのは、技術に意味を与えるため。どちらかではなく、どちらも。ギタリストとして進んでいくには、その両輪が必要だ。
そして結局、こういう話って
要はコンプレックスの話だ。
技術の人は、自分の努力を軽く扱われるのが許せない。
気持ちの人は、自分の表現を技術で否定されるのが怖い。
立場を守りたいから、相手を否定する。
ただ、ギターに没頭していたらそんなこと気にもならない筈だ。
自信の無さから不安を他人にぶつけて少しでもポジションを上げようとしているのではないだろうか。
実は普遍的な論争の中心に“本気で取り組む人”は少ない。
そう思うと没頭こそが唯一の救いなのかもしれない。







