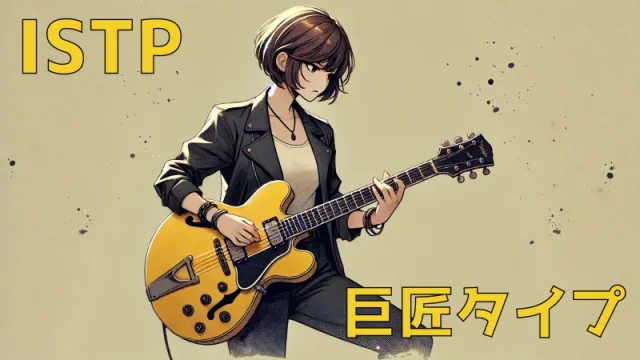圧倒的にギターが上手くなりたいなら他者との比較を辞めてはいけない。

「人と比べるな」
この言葉が言われるようになって久しい。とくに近年では、SNSや評価社会に疲れた人々にとって、それは救いのようなメッセージになっている。
この考え方には、ちゃんと理由がある。
過度なプレッシャーを避け、健全な精神状態を保つことが、結果として高いパフォーマンスにつながる。だからこそ「自分は自分でいい」と思える環境が重要だと言われるようになった。
公式ページnd=”391″>たしかに、音楽の世界で芯を持って生きている人たちは、他人と比べることすらしない。
芸術や芸能の分野は、スポーツのように誰かと競り合うことで結果を決める世界ではない。
むしろ「いかに他と違うか」という個性こそが、評価の軸になることも多い。
しかし一方で、ギターという楽器の世界には——
明確に他人と比べられる側面が存在するのも、また事実だ。
例えば、技術。知識。対応力。演奏の精度や表現の幅。
それらは数字では測れないが、音を聴けば、誰が上手いかは分かってしまう。
そして、ときに“圧倒的な能力”を持つ人は、それ自体が個性として認識されることもある。
つまり、比べることを完全に否定してしまっては、本質を見失う可能性がある。
誰かと比べることでしか見えない“自分の現在地”がある。
そして、そこから抜け出したいという欲が、次の成長を生む。
本気でギターで抜きん出たいなら、誰かと比べることをやめてはいけない。
ここから、その理由を語っていく。
比べることは悪じゃない
人と比べることでしか、自分の立ち位置は分からない。
「今の自分はどれくらい弾けるのか?」
「何ができて、何ができていないのか?」
これらを知るには、他人の演奏という“鏡”が必要だ。
そして、目の前の誰かが自分より上手かったとき、こう思うはずだ。
「なんで、あいつは俺より弾けるんだ?」
この疑問を、悔しさに変えられる人間は強い。
なぜあいつは俺より弾けるのか?
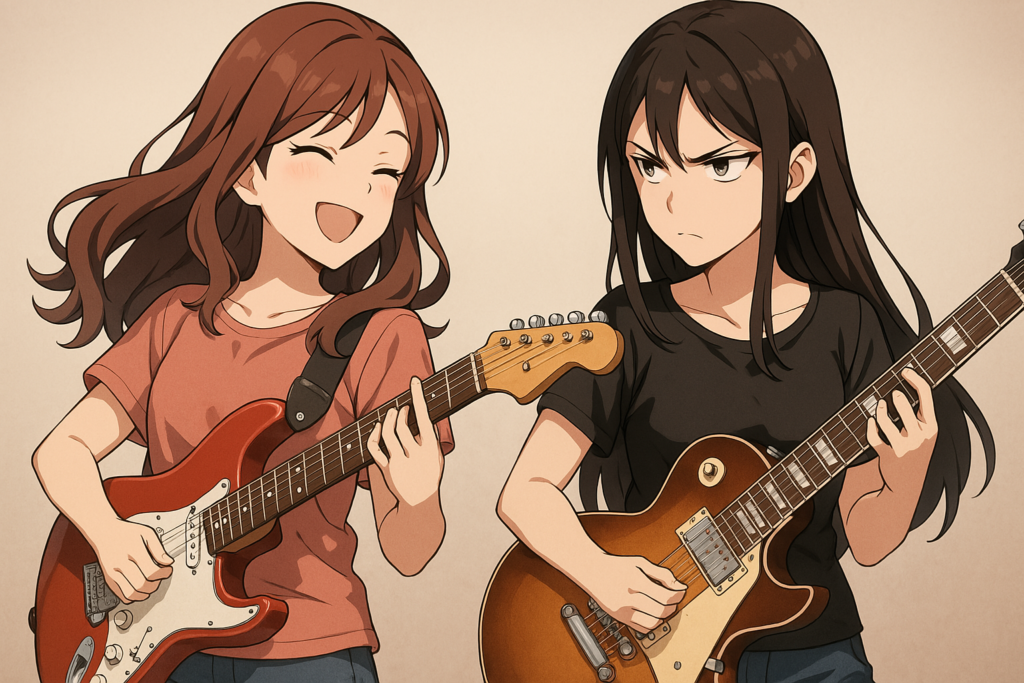
ここを突き詰めることが、まさに研鑽のスタート地点になる。
・テクニックが足りないのか?
・リズム感に差があるのか?
・音作りにこだわっているのか?
・表現力に“引き出し”の差があるのか?
分析しよう。考えよう。そして、素直に学ぼう。
時には「教えてください」と頭を下げることも、上達への近道だ。
“悔しい”という気持ちを、逃げずに直視できる人は、確実に前に進める。
比べる相手は選べ
ただし、誰と比べるかは慎重に考えるべきだ。
方向性もジャンルもレベル感も違う相手と自分を比べても、自己肯定感が削られるだけで終わってしまう。
重要なのは、自分と「少し先を歩いている人」を探すこと。
その人の音を聴いて、「ああ、これなら背中が見えるかも」と感じるなら、それはもう最高のベンチマークになる。
YouTubeの弾いてみた動画、Instagramでの演奏投稿、ライブハウスで出会った誰か。
比較の対象は、ネットにもリアルにも無限にある。
比較から、自分の強みを見つける
人と比べるからこそ、自分の“武器”が見えてくる。
「この人は速弾きがすごい。でも自分はビブラートで勝負できる」
「あの人は正確さがある。でも自分にはエモさがある」
全体で勝とうとする必要はない。部分で、尖ればいい。
そしてその“尖り”が、やがてあなたの音楽を支える芯になる。
比べてヘコむか、燃えるか
ここが一番大切だ。
あなたは、人と比べて落ち込むタイプか? それとも燃えるタイプか?
もし、前者なら——
まずは自分のメンタルと向き合うところから始めよう。
どちらにせよ比較で落ち込むような状態という事は自信がない証拠。
「今の自分」を認めてあげるだけでも伸び伸び取り組む事が出来るだろう。
また、自分の内側からあふれる好奇心に素直に従う事であなたらしさを獲得できる。
他所は他所、自分は自分。そういうメンタルを育てていこう。
でも、後者なら——
その火を、恐れずに燃やし続けてほしい。
悔しさや嫉妬心にちゃんと向き合える人間は、強い。
ギターの世界に“優しさ”だけでは届かない領域があることを、もう知っているはずだ。
比べることを恐れるな
「人と比べなくても良い」
そんな優しい言葉に、違和感を覚えたことはないだろうか?
もしかしたら、それが逆に生きづらさになっている人もいるかもしれない。
でも、比べてしまうあなたは、弱いんじゃない。
強くなりたいと願っている証拠だ。
正しく比べて、正しく研鑽を積めば、あなたはきっと“圧倒的な個人”になれる。
恐れるな。比較は、成長の武器だ。