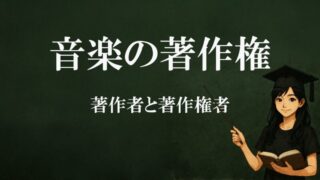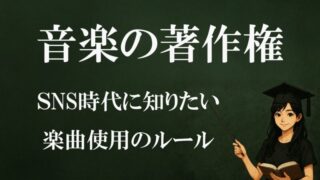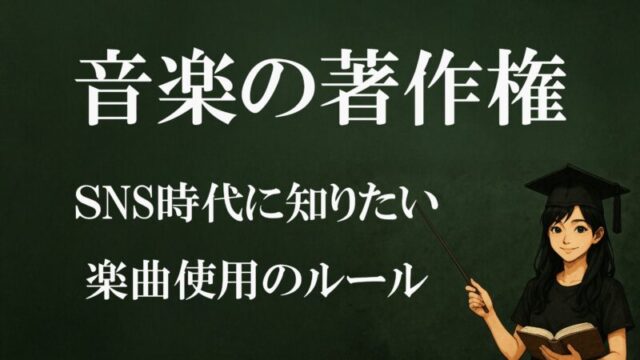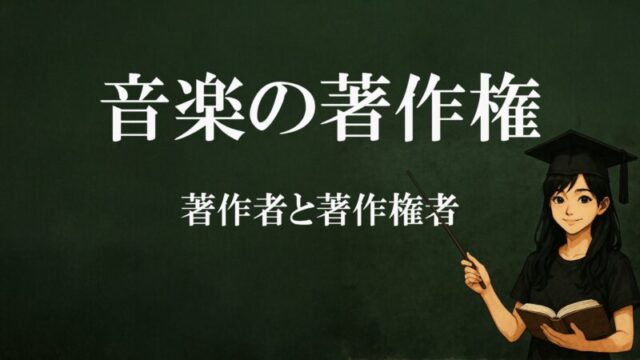著作者の善意に支えられた「弾いてみた」文化|SNS音楽活動の注意点
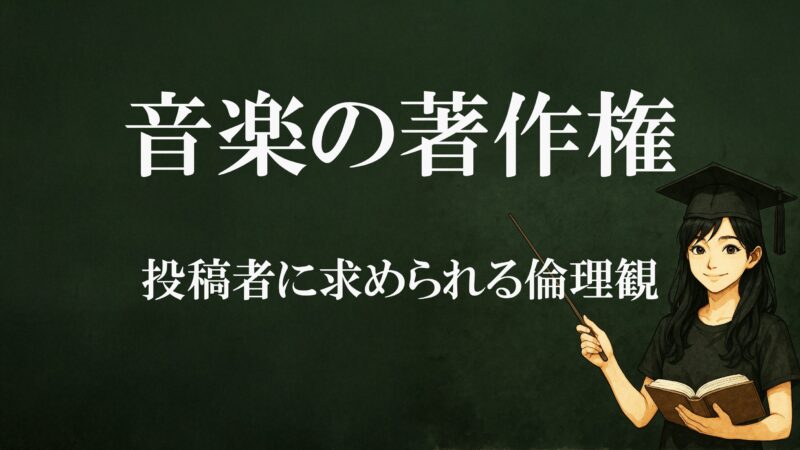
ギターを弾く人なら、SNSやYouTubeに投稿されている「弾いてみた」動画を一度は見たことがあると思います。
そうやって趣味の音楽活動をしている人は、本当にたくさんいます。
「弾いてみた」動画やカバー演奏は、純粋に楽しいですし、上達のモチベーションにもなります。
再生数が伸びれば嬉しいし、同じ趣味の人とつながるきっかけにもなります。
SNS全盛の今、こうした“演奏の共有文化”はすっかり広く普及しています。
けれど、その活動の多くは、法律的にはグレーなゾーンを著作者が黙認してくれているおかげで成立している、という現実もあります。
著作権者に“指摘されていない”だけ。
結論から言えば、SNSでの演奏動画の投稿は、必ずしも違法になるわけではありません。
たとえばYouTubeやInstagramなど、一部のプラットフォームはJASRACやNexToneと包括契約を結んでおり、管理楽曲については一定の範囲で演奏や投稿が認められています。
これは、演奏者にとって非常にありがたい環境と言えます。
とはいえ、それは「許可されたから自由にやっていい」という意味ではありません。
著作者(=作曲者や作詞者)が明確に「カバー自由です」と宣言したわけでもなく、レーベルや出版社がすべての動画に目を通して個別に許諾を出しているわけでもないからです。
つまり、違法ではないが、正式に“OK”をもらっている状態ではないという点は、きちんと押さえておく必要があります。
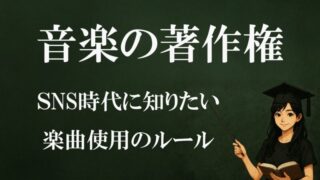
SNSでの音楽活動は“著作者の善意”の上に成り立っている
多くの著作者は、自分の曲がコピーされ、自由に演奏され、広まっていくことに対して、ある程度寛容な姿勢を見せてくれています。
それは、楽曲が「愛されている証」として受け取ってくれているからです。
ただ、それは裏を返せば、著作者の気持ち次第でいつでも態度が変わりうるということでもあります。
実際に、あるアーティストが「改変されたアレンジに不快感を覚えた」として、SNS投稿に対して指摘を行った事例もあります。
「カバーされること自体は嬉しい。でも、自分の意図とは違う形で使われるのは望んでいない」と語る著作者も、決して少なくありません。
SNSで公開されている多くの演奏は、そうした著作者の“暗黙の許容”によって支えられているのが実情です。
言い換えると、演奏者は著作者の“善意に甘えている”状態とも言えるでしょう。
著作物は“共有財産”ではない
音楽は誰かの創作物であり、著作者にとっては財産であり、表現であり、アイデンティティそのものでもあります。
それを見知らぬ誰かに勝手に使われたり、意図を変えられたりすることは、決して気持ちの良いものではないはずです。
特に問題になりやすいのが、次のようなケースです。
- 原曲をアレンジして、まったく違う雰囲気に変えている
- クレジット(作詞・作曲者名)を記載していない
- 替え歌にしてしまっている
- 動画の収益化をしている
こうした行為は、たとえ法的に完全な違法とは言えなかったとしても、著作者からすると「勝手なことをされた」と感じられてしまう行動です。
“違法じゃないから自由”ではなく、“許されていることに感謝”する姿勢を持つべき
たとえば、好きなギタリストの曲をコピーして動画にする場合、
「この曲を演奏できて本当に嬉しいです。素晴らしい楽曲をありがとうございます」と、
ひと言でも書いてある投稿を見ると、見ている側もとても気持ちよくなります。
その一方で、「無断転載・無許可アレンジ・ノークレジット・収益化」などが揃っている投稿を見ると、正直、悲しい気持ちになってしまうこともあります。
それは演奏の上手い・下手の問題ではなく、姿勢の問題です。
音楽を創った人へのリスペクトや、感謝の気持ちがきちんとあれば、
自然と投稿内容や言葉選びにも気を配るようになるはずです。
演奏者としての良識と責任を持とう
ギターを弾く人も、演奏をSNSにアップする人も、どちらも素晴らしい音楽文化の担い手です。
だからこそ、著作者の気持ちを理解し、尊重する姿勢が求められていると思います。
「著作権的に問題ない範囲だからOK」ではなく、
「著作者が嫌がるような使い方をしていないか?」という視点を、常に忘れないようにしたいところです。
そのうえで、
- クレジットをしっかり書く
- 商用利用は控える
- 改変や編集は慎重に行う
- コメント欄や概要欄で、楽曲に対する敬意や感謝をきちんと伝える
といった配慮ができれば、演奏活動はもっと気持ちよく続けられるはずです。
まとめ|“許可されていないけど許されている”という現実を理解しておこう
- SNSでの音楽活動は、法的にはグレーゾーンである場合が多い
- それでも著作者が黙認してくれているケースが多く、善意によって支えられている
- 「違法じゃないからOK」という姿勢のままでは、いずれトラブルになる可能性がある
- 著作者への敬意と感謝を忘れず、良識ある活動を心がけることが大切
演奏者と著作者のあいだに“信頼関係”が生まれれば、SNS上の音楽活動はもっと自由で、もっと楽しくて、そして持続可能な文化になっていくはずです。
ギターを楽しむ一人のプレイヤーとして、自分の表現が誰かの創作の上に成り立っていることを、これからも忘れずにいたいですね。