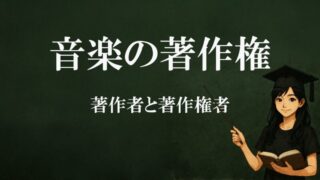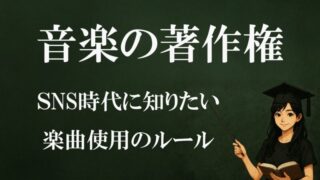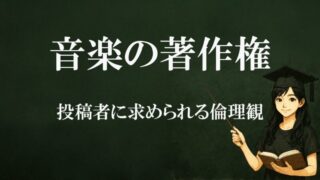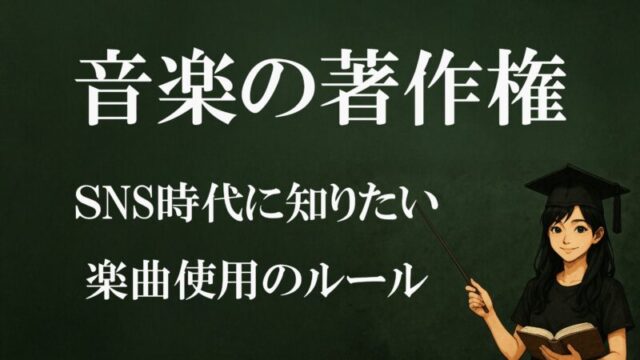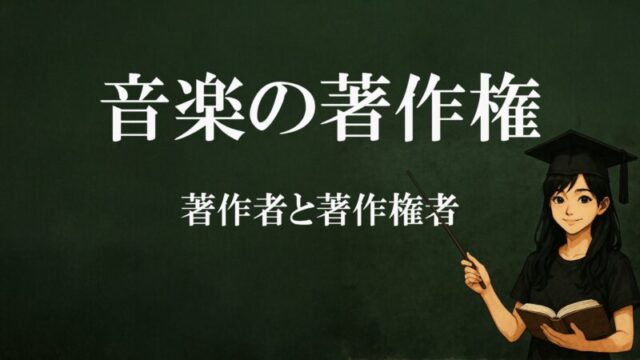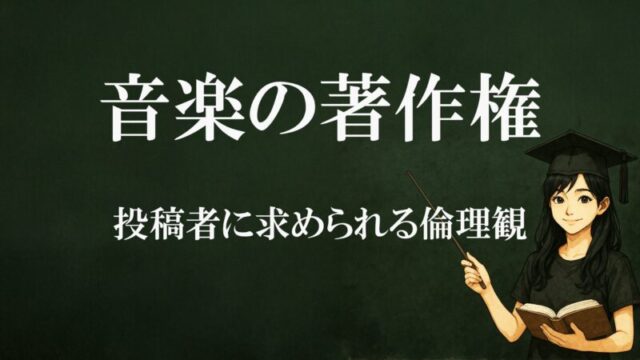AI作曲は是か非か|創作する事に対する”倫理観”が問われる時代

「AI作曲なんて邪道だ」──そう思っていないでしょうか?
最近は、AIが作った楽曲を耳にする機会がかなり増えてきました。
SNSでも「人間の感情がこもっていない音楽に価値はあるのか?」といった議論が交わされています。
そう言いたくなる気持ちも、正直よく分かります。
音楽は感情であり、想いであり、ストーリーだ──という価値観には、筆者も強く共感しています。
それでもあえて筆者は、「AI作曲は是である」と断言したいのです。
なぜなら、それは音楽の本質を壊すものではなく、むしろ音楽の可能性を広げてくれる技術だと考えているからです。
作曲が「選ばれた人」だけの特権だった時代はもう終わる
これまで作曲は、一部の“才能ある人間”だけに許されたスキルのように扱われてきました。
理論を学び、DAWを使いこなし、試行錯誤を重ねて、ようやく「曲」と呼べる形になる。
興味はあっても「どうやって始めればいいのか分からない」と感じていた人も多かったのではないでしょうか。
AI作曲ツールは、まさにその“始めたくても始められなかった人”にとっての希望になり得る存在です。
やり方が分からない、理論が分からない、時間がない──
そういった壁を取り払って、「まずは曲を作ってみる」という体験をさせてくれるようになりました。
作曲をしたことがある人なら共感してもらえると思いますが、こうした“取っ掛かり”はとても重要で、
「作曲は難しい」という固定観念を一度壊すことが、作曲の第一歩になったりするのです。
作れるようになることで、改めて“作る価値”が問われている
誰でも曲を作れる時代になりました。
では、それによって曲の価値は下がるのか? いいえ、必ずしもそうとは言えません。
むしろ、「自分で作る」ことの意味や、「人間が作る」ことの価値が、以前よりもはっきり問われるようになってきたと感じます。
AIで作曲できるようになったからこそ、
「なぜ自分はこの曲を作りたいのか」
「このメロディにどんな感情を込めたいのか」
といった人間ならではの動機や背景が、よりクローズアップされるようになりました。
「誰が作ったか重視されない音楽」も確かにある
たとえば、スーパーの店内BGM、ゲームアプリの効果音、ラジオジングルなどです。
こういった用途では、「誰が作ったか」よりも「その場の雰囲気に合っているかどうか」の方がずっと重要です。
その意味では、AIが作った曲でも何の問題もありません。
そして、そうした領域をAIが担ってくれるのであれば、人間の作曲家はそこに貴重な時間を割かずに済み、音楽制作全体の効率化にもつながります。
かつてボーカロイドも否定された。でも文化は広がった
ボーカロイドが登場した当初は、「機械の声には感情がない」「やっぱり人間が歌うべきだ」といった否定的な声も多くありました。
しかしふたを開けてみれば、“歌い手”文化が育ち、多くのクリエイターがボカロをきっかけに曲作りを始めました。
その結果、音楽を作る人・歌う人・聴く人の裾野は大きく広がったのです。
AI作曲も同じように、音楽文化を一歩先に進める力を持っていると、筆者は感じています。
「AIの方がいい曲作るからムカつく」──それ、違う
ときどき、「AIに自分より良い曲を作られたらどうするんだ」という意見を目にします。
ですが、それは自分の価値を“曲の良し悪し”だけに預けてしまっているから、しんどくなってしまうのではないでしょうか。
AIは、確かに「良い曲」を作ることができるかもしれません。
しかし、その曲に動機や人生、ストーリーを宿すことはできません。
時間をかけて創作に向き合うことができるのは、あくまで人間だけに与えられた特権です。
リスナーは“誰が作ったか”にも価値を感じている
今のリスナーは、「ただ良い曲を聴きたい」というだけでなく、
「この人がどんな思いでこの曲を作ったのか」といった背景や人格にも魅力を感じて、ファンになります。
YouTuberやインディーアーティストにファンがついていくのも、その“人”への関心があるからです。
だからこそ、人間が曲を作る意味はこれからも失われません。
むしろ、AIが台頭することで“人間らしさの重要性”が、よりくっきりと浮かび上がってくるだけだと思います。
【注意喚起】「作曲者を名乗るのは危険かも?」

■ AI作曲が当たり前になってきた今、「誰の曲か?」があやふやになっている
AI作曲ツールを使えば、数クリックでメロディ・コード・構成まで自動生成できる時代になりました。
「自分で作った」と言いたくなる気持ちも、もちろん分かります。
ですが、そのひと言がトラブルや炎上、著作権問題につながる可能性もあるのです。
実際、「AIが生成した曲」に対して人が“作曲者”を名乗ってよいのかどうか、という問題は非常にセンシティブです。
以下で、具体的なケースごとに整理してみます。
ケース①:プロンプトを打ち込んだだけで、AIの出力をそのまま使用した場合
❌ 基本的に“作曲者”とは名乗れない可能性が高い
プロンプト(指示文)を入力しただけで、メロディ・コード進行・構成のすべてをAI任せにしている
出力された内容に対して、自分の手では一切手を加えていない
このようなケースでは、“自分が作曲した”とは言えないと解釈される可能性が高いです。
たとえば、画像生成AIに「夕暮れの海を描いて」と指示して出てきた絵を、自分の“画家としての作品”として発表するようなイメージに近いでしょう。
● 法的にはどうなる?
現状、日本ではAIが作った作品には著作権が発生しない(=無主物)とされています
そのため、そのまま商用利用すること自体は可能ですが、「自分が作曲した」と主張するのはグレーです
さらに、AIが学習・参考にしたデータの中に他人の著作物が含まれていた場合、類似曲問題に発展するリスクもあります
● SNS・YouTubeでも注意
「作曲しました」とタイトルに書いてしまうと、炎上や批判の対象になる可能性があります
特にプロとしての活動を視野に入れている場合、“虚偽の経歴”と受け取られるおそれもあります
ケース②:AIの出力をベースに、手直し・編集を加えた場合
✅ 編集の度合いによっては「作曲した」と言えることもある
メロディの譜割り(リズム)を変更した
コード進行を差し替えた
曲の展開(構成)を再構築した
アレンジだけでなく、音楽的な判断を自分で行っている
このような編集を行っている場合、「AIの支援を受けつつ行った共同作業」として、一定の“作曲性”が認められる可能性があります。
● ただし“どこからが自作か”の線引きは曖昧
単なる置き換えレベルの変更では「改変」にとどまり、“作曲者”と名乗るには弱い
ゼロから自分の頭で考えて組み立てたかどうかが、ひとつの判断基準になります
道義的には、「AIを使いました」と明記しておく方が誠実、というのが現状です。
ちょうど加工食品の原材料名に添加物を明記するような感覚が求められていると言えます。
AIを使って曲を作るなら、名乗り方に注意しよう
| 作業内容 | 作曲者を名乗れる? | 注意点 |
|---|---|---|
| プロンプトだけ → 完全自動生成 | X 原則NG | 虚偽表示と受け取られる可能性が高い/信用問題にも直結 |
| 軽微な修正(テンポ・楽器など) | △ 非推奨 | 作曲とは呼びにくく、“アレンジ”扱いになる |
| メロ・コード・構成を手直し | ◯ 条件付きOK | “AIアシストで作曲”などと明記しておくと安心 |
| AIを参考にしつつ自分で構築 | ◎ 問題なし | AI使用をあえて伏せる必要もなく、堂々としていて良い |
AI作曲時代の“名乗り方ガイド”
AI作曲をした場合は、「AI作曲」と明記しておくのがおすすめです。
完全自動生成なら、「作曲した」ではなく「生成した」「AIで作った」といった表現を選ぶ
手直しを加えた場合も、“一部AIで補助”などと書いておくと、後々のトラブルになりにくい
商用利用やクレジット表記では、「作曲(AI)/編集(あなた)」のように役割を分けて表記するのが安全
筆者としては、AI作曲そのものは肯定していますが、
その成果物に対する“クレジットの扱い”については、以前より慎重さが求められる時代になってきたと感じています。
「盛りすぎた表現」は、結局のところ信頼を失う原因になりがちです。
AI時代の音楽家には、作品とどう向き合うかという倫理観こそが、“センス”の一部として求められてくるのかもしれません。
AI作曲は音楽を殺すのではなく、広げる存在
AI作曲によって、音楽が壊されてしまうのではないか──そんな不安の声があるのも理解できます。
ですが筆者は、むしろ創作を拡張し、民主化し、もう一度捉え直すためのチャンスだと考えています。
・これまであきらめていた人が、曲を作れるようになった
・「誰が作るのか」が、より問われる時代に入った
・人間が作ることの意味が、かえってはっきりしてきた
AIは敵ではありません。
音楽を作るためのひとつの手段として、上手に付き合っていけば良いのだと思います。