「ブースターとしても使える歪みエフェクター」ってどんな特徴があるの?

「この歪みエフェクター、ブースターとしても使える」
エフェクターのレビューでこんな言い回しを目にすることがある。実際に機材を使い込んでいるギタリストなら何となくニュアンスで理解できるかもしれないが、まだギター歴が浅い人や、これから機材選びを始めようとしている人にとっては、その“ブースターとしても”という言葉の意味が分かりづらいのではないだろうか。
「歪み」と「ブースター」。それぞれ単体で理解することはできても、それを一台のペダルにどう結びつけるのか、その使い分けはどう考えるべきか。そのあたりをしっかり把握することは、音作りにおいても、エフェクター選びにおいても大きな助けになる。
この記事では、「ブースターとして使いやすい歪みエフェクター」に共通する特徴を整理しながら、なぜそう言えるのかを実例を交えながら解説していく。さらに後半では、あえてその“セオリー”を外していく楽しみ方についても触れる。
なぜ歪みエフェクターをブースターに?
まず前提として、「ブースター」とは何か。
ブースターは、シンプルに言えば“信号を増幅させる役割”を持つエフェクターだ。歪ませるのが目的ではなく、主には音量(出力)や押し出し感を上げるために使用される。
しかし、実は歪みエフェクターにもこの「ブースター的な使い方」が可能なモデルがある。それも、ほんの一部ではなく、わりと多くの機種がそのポテンシャルを持っている。とはいえ、すべての歪みペダルがブースターに向いているわけではない。
ここで重要になってくるのが、「どんな特徴を持つ歪みペダルがブースターとして使いやすいのか?」という視点だ。
① ゲインを下げても綺麗に鳴るかどうか
最初に見るべきは、「ゲインを最小にしたときの音質」だ。
ブースターとして使用する場合、歪みは極力控えめにし、信号の強さや音のキャラクターだけを後段に伝えることが求められる。つまり、ゲインが低い設定でも音が濁らず、クリーンに近い状態で使えるかどうかが重要になる。
たとえばBOSSの「BD-2(Blues Driver)」は、設定によっては激しいオーバードライブにもなるが、ゲインを絞ることで“ほぼクリーン”とも言える状態にすることができる。クリーンブースター代わりに使えるだけでなく、アンプの入力をプッシュするような自然な音圧アップにも使える。こういった柔軟性のあるペダルは、ブースターとしての適性が高い。
ゲインが下がると急にペラくなったり、歪みが抜けきらない機種はブースターとしてはやや不向き。逆に、低ゲインでも張りのある音が出る機種はかなり重宝する。
② 出力レベルのレンジが広いかどうか
ブースターとして使う以上、当然ながら「レベル(音量)」の調整範囲が広い方が便利だ。
ペダル自体の出力が高ければ高いほど、後段の機材——たとえばアンプのプリアンプ部や別の歪みペダル——を強くプッシュすることができる。
「レベルが上がるだけでしょ?」と思うかもしれないが、実はこれが音の立ち上がりやパンチ感、サスティンの伸びに大きく関わってくる。レベルをしっかり上げられる歪みペダルは、音作りにおける“芯”を補強する役割として非常に有効だ。
③ 特定の帯域にキャラがあるか
音が「前に出る」か「埋もれる」か。その差を生み出すのは、EQ(音の帯域バランス)の個性だ。
特に、ミドルが強調されているペダルはブースター用途として優秀な傾向がある。ギターの音はもともとミッドレンジ(中域)に多くの成分を持つため、そこを押し出してくれるペダルは“抜ける”サウンドになりやすい。
チューブスクリーマーがなぜ長年ブースターとして使われてきたのか。それは、あの“鼻詰まり系”とも言われるミドルのキャラクターが、バンドアンサンブルの中でギターの存在感を際立たせてくれるからだ。
一方で、ミドルが弱い、もしくは全帯域がフラットなエフェクターは、ブースターとして使うとややパンチに欠ける印象になりやすい。だが、それが逆にナチュラルな仕上がりになることもあるので、一概には言えない部分もある。
あえてブースターとして使ってみるという楽しみ方
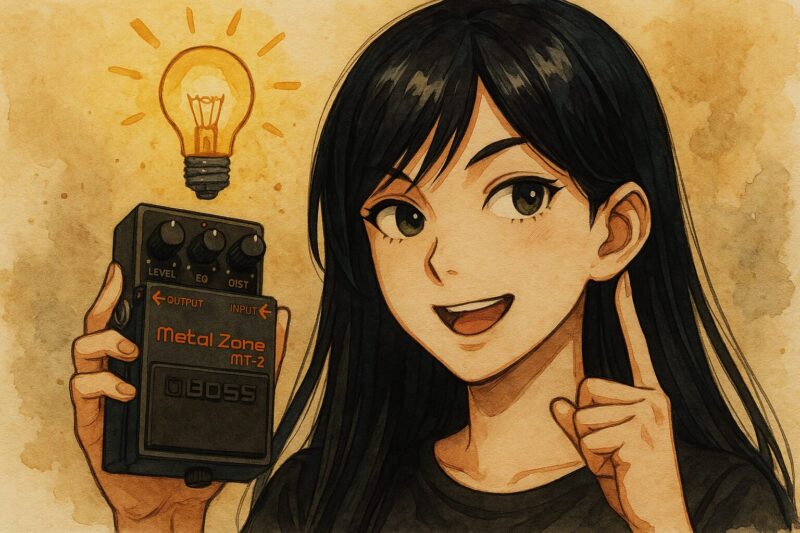
ここまでは“ブースターとして使いやすい”歪みペダルの条件を挙げてきた。しかし、それに当てはまらない機種をブースターとして使ってはいけないのかというと、そんなことはまったくない。
むしろ、「本来はブースター向きじゃないけど、試しにやってみたら意外と良かった」という発見があったりする。たとえばファズペダル。ブースター用途としてはあまり語られないが、ファズフェイスなど一部のモデルは、ゲインを抑えてレベルを上げると非常に面白い効果が得られる。倍音感が増したり、トーンに独特のザラつきが加わったりする。
要は、「そのペダルをどう使うか」というのはマニュアルに書かれた通りだけじゃなく、自分なりに実験して楽しむのが本質だということだ。個性的なエフェクターを敢えてブースターとして使うという発想自体が、ギタリストとしての“引き出し”を増やすことにもつながる。
一台で二役こなす歪みエフェクターと、その先にある実験の楽しみ
歪みエフェクターをブースターとして使う。
それは単に「省スペースで済む」という合理性だけでなく、1台のエフェクターに多彩な可能性を見出す楽しみでもある。
もちろん、今回紹介したような“ブースター向き”の特徴を備えたペダルを選べば、失敗は少ないし、扱いやすい音が得られるだろう。だが、それは裏を返せば「無難」であるとも言える。尖った個性や驚きには欠けるかもしれない。
一方で、「このエフェクターをブースターに使ったらどうなるんだろう?」という遊び心から始まる実験は、まさに歪みエフェクターの醍醐味。
歪みエフェクターは、単なる歪み装置ではなく、“ブースター”、“EQ補正”、“音圧調整”など、さまざまな役割を試せる実験道具だとも言える。
その柔軟性があるからこそ、ギタリストたちは何台もの歪みペダルを並べては、ああでもないこうでもないと試行錯誤を繰り返す。そうやって、自分だけの音、自分だけの使い方を見つけていくのだ。
だからこそ、一見合わなさそうなエフェクターでも、まずは繋いでみて欲しい。意外な化学反応が、あなたのサウンドを進化させるかもしれない。







