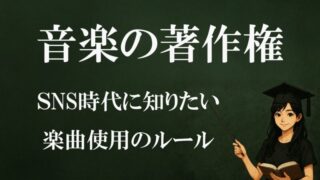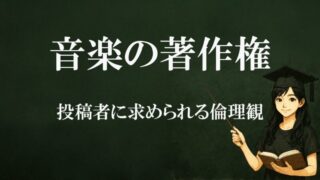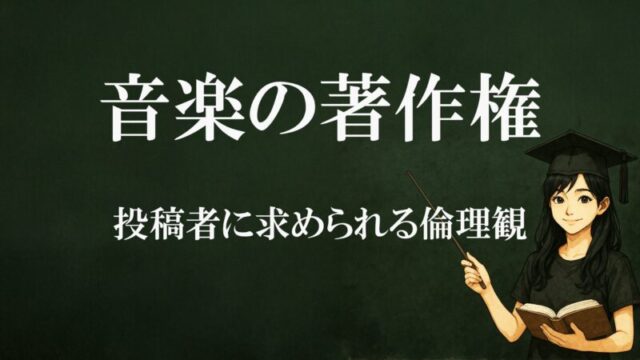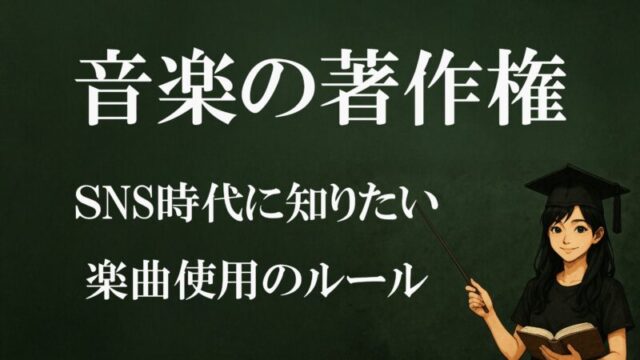「弾いてみた動画」で著作権トラブル?著作者・著作権者・人格権の違いを解説
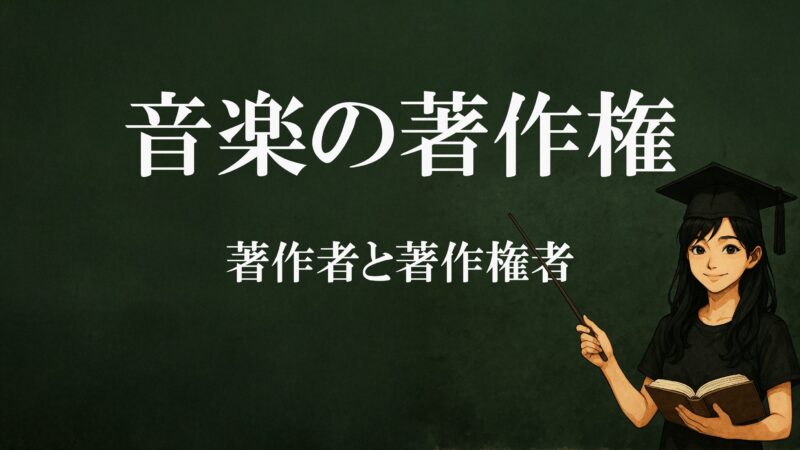
SNSやYouTubeで「弾いてみた」や「カバー演奏」動画をアップする人がどんどん増えています。
ギターや音楽を愛する身としては、誰かの曲を自分なりに表現したいという気持ちには、本当に強く共感します。
しかし、その“善意”や“憧れ”から生まれた表現が、思わぬトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
とくに著作権に関する理解が不十分なままだと、アカウント停止や削除要請、最悪の場合は法的措置にまで発展してしまうこともあります。
今回は、弾いてみた動画を投稿するうえで知っておきたい「著作権者と著作者の違い」、そして意外と見落とされがちな「著作者人格権」についても掘り下げて解説していきます。
「バックトラックに原曲使用」は特に危険
まず最初に強く注意しておきたいのが、バックトラックに原曲そのものを使用しているケースです。
「カラオケ音源を流して、その上に自分のギターを重ねて演奏する」というスタイルは、視聴者にとっては馴染みやすいかもしれません。
しかしこれは、原曲の著作物を無許可で使用している可能性が非常に高い行為です。
演奏部分は自分のオリジナルであっても、背景で流れているのが市販音源やYouTubeなどから抜き出した原曲であれば、それだけでアウトになってしまう場合があります。
さらに、こうした音源はYouTubeの自動検出システム(Content ID)などによって簡単に見つかってしまいます。最悪の場合、動画の収益化が無効になるだけでなく、動画自体が削除されたり、アカウントにペナルティが課される可能性もあります。
できる限り、バックトラックも自作するか、ライセンスが明示されているフリー音源を使うようにしておきたいところです。
手間はかかりますが、のちのトラブルを避けるための“自分の身を守る行動”になると思っておきましょう。
著作者と著作権者は同じじゃない
ここで、一度基本的な用語を整理しておきます。
- 著作者(ちょさくしゃ):作品を実際に創作した人のことです。作曲家・作詞家・編曲家などがこれに当たります。
- 著作権者(ちょさくけんしゃ):著作権を持っている人(または法人)のことです。著作者がそのまま権利者である場合もあれば、レーベルや事務所などの法人が権利を保有している場合もあります。
たとえば、あるアーティストが自分で作った曲であっても、その楽曲を所属レーベルに売却したり、管理を委託したりすると、著作権者はその法人側になります。
これは業界ではよくあることで、商業的なマネジメントや配信、使用許可の管理などを効率化するための仕組みです。
スティングが権利を売却した話
分かりやすい例として、2022年にスティングが自身の作品の著作権をレーベルに売却したという事例があります。
これは、一時的に大きな収益を得るという意味での“キャッシュ化”であると同時に、管理やライセンス業務を手放すという選択でもありました。
スティングは見た目はスマートなイケオジですが、すでに70歳を超えた高齢のアーティストでもあります。 彼が亡くなった後は遺族が権利を引き継ぐことになりますが、その場合、ライセンスや管理業務も同じように引き継がれることになります。
確かに、継続的な印税が発生するのは遺族にとって大きなメリットですが、その分、管理業務の負担も背負うことになります。
であれば、将来的な印税と売却益をトレードしてしまう、という選択肢も悪くないわけです。
ビッグアーティスト流の“終活”の一つとして、今後こういった選択をする人はますます増えていきそうです。
著作者人格権とは?知らないと危ない権利
著作者は、たとえ著作権を譲渡したあとでも、決して手放すことのできない“もう一つの権利”を持っています。
それが「著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)」です。
この権利は著作者個人にしか認められておらず、他人に譲渡したり、相続したりすることができません。内容は次の3つに分けられます。
- 公表権:作品を公開するかどうか、そのタイミングを含めて決める権利
- 氏名表示権:作品に自分の名前を表示するかどうか、匿名・ペンネームにするかを決める権利
- 同一性保持権:作品を無断で改変されないように守る権利
この「同一性保持権」が特に問題になりやすいのが、動画投稿における大胆なアレンジや、曲の構成・メロディを大きく変えたカバー演奏です。
「自分なりに解釈してオシャレにアレンジしたつもり」でも、著作者から見ると「もう原型をとどめていない」「自分の作品が傷つけられた」と感じられてしまうこともあります。
つまり、どれだけ著作権者が「使用していいですよ」と許可していたとしても、著作者の人格権を侵害してしまえば、それは立派な権利侵害として扱われるということです。
著作権と著作者人格権の違いを表で整理
| 種類 | 権利者 | 譲渡 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 著作権 | 著作権者(法人含む) | 可能 | 複製、頒布、公衆送信、上映、翻訳などの経済的権利 | 金銭的価値あり |
| 著作者人格権 | 著作者個人のみ | 不可 | 公表・氏名表示・同一性保持など、作品の人格的側面を守る | 一身専属で法律により守られる |
このように、両者は根本的に異なる性質の権利であり、「許可を取ったから大丈夫」と思っていても、それだけでは十分でないケースがあるということです。
弾いてみた文化は著作権者の“善意”の上に成り立っている
最近では、JASRACやNexToneなどを通じて、一定のルールに従えばカバー投稿が認められる仕組みが整いつつあります。
YouTubeにも「JASRACと包括契約を結んでいるため、許可不要」とされるケースがありますが、これはあくまで条件付きで、すべての状況に当てはまるわけではありません。
・編曲の範囲が大きい
・商用利用している(広告をつけて収益を得ている)
・海外の曲で、管理の対象外になっている著作物が含まれている
こういった条件が絡んでくると、一気にリスクは高くなります。
最終的には著作権者の裁量に委ねられている部分も多く、「暗黙の了解」で成り立っている面が少なくないのが実情です。
だからこそ、投稿する側が最低限の法律知識を身につけたうえで、著作物に対する敬意とリスペクトを持って行動することが大切です。
知識を持って、自分の演奏活動を守ろう
ギターでの「弾いてみた」や「カバー演奏」は、演奏力や表現力を育てるうえでとても良い手段ですし、視聴者とつながるきっかけにもなります。
ただ一方で、著作物を扱うということは、その背後にいるクリエイターの権利や感情と向き合うことでもあります。
特に、著作権と著作者人格権の違いを理解していないと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。
自作のバックトラックを使う、権利の所在をきちんと確認する、そして何よりリスペクトを忘れない。
音楽は自由な表現であると同時に、法律とモラルのバランスの上に成り立っている――そのことを頭の片隅に置きながら、演奏活動を続けていきたいところです。