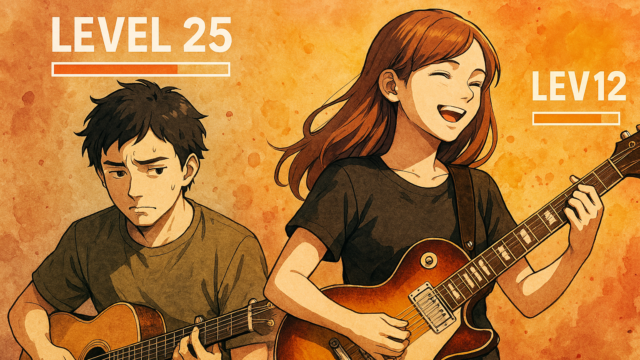ギター機材レビューの見極め方|通販・動画・実店舗を駆使する賢い選び方

ギターを趣味として続けていると、必ず訪れるのが機材選びのタイミング。
新しいエフェクターやアンプが気になったとき、真っ先に頼りたくなるのがネット上のレビューだ。
サウンドハウスなどの通販サイトには、実際に購入したユーザーのレビューが数多く投稿されており、評価や感想をざっと読むだけでも参考になりそうに思える。
さらに最近は、YouTubeなどでインフルエンサーや楽器店がレビュー動画を公開しており、映像と音で機材の特徴を確認できる時代になっている。
一見、「これだけ情報があれば安心!」と思いがちだが、実際にはレビューは玉石混交。
情報の取り扱いを間違えると、「思っていたのと違う…」という機材選びの失敗につながりかねない。
そこで今回は、筆者が普段から意識しているレビューの見極め方を紹介していく。
サウンドハウスのレビューを例に挙げながら解説するが、内容は通販レビューと動画レビューの両方に応用できるものだ。
正しい情報を選び取り、あなたの機材選びがさらに納得のいくものになるよう、ぜひ参考にしてほしい。
なぜレビューを慎重に読むべきか?

まずは基本的な考え方を整理しよう。
レビューはあくまで個人の感想だ。
それってあなたの感想ですよね。ってやつ
レビューを書いている人の、
演奏スキル
機材環境
好きなジャンルや音作りの好み
──こうした背景がまったく違う場合、自分にとってはあまり参考にならない可能性がある。
特に通販サイトのレビューは、投稿者のキャラクターがわかりづらい。
誰が、どんな環境で、どういうシチュエーションで使った感想なのか?
これが見えなければ、いくら星の数が高くても「自分に合うかどうか」の判断材料にはなりにくいのだ。
信頼できるレビューの条件
筆者がレビューを読むとき、まず重視するのは「使用環境がはっきりしているか」という点だ。
たとえば次のような情報がしっかり書かれていると、とても参考になる。
✅ どんな環境で使ったか?
使用ギター(例:ストラトキャスター、レスポール、テレキャスターなど)
アンプの種類(例:マーシャル、フェンダー、トランジスタアンプか真空管アンプか)
エフェクターボードの中でどこに配置しているか
こうした情報は、同じような環境で使う予定の人にとって非常に有益だ。
例えばあるレビューでは「マーシャル系アンプのクリーンチャンネルに接続して使った」という記載があった。自分が同じような環境なら、そのレビューはかなり信用できる。
✅ どんなジャンル・シーンで使っているか?
ブルースでクランチ主体
ハードロックでリード用に
宅録メインかライブメインか
など、具体的な使い道がわかるレビューも信頼できる。たとえば「ジャズでバッキングに使っている」「ブルースセッションで常時オンにしている」など、ジャンルがわかると自分の使い道と重ねて考えやすい。
✅ 他機材との比較があるか?
レビュー内で「他の似たペダルと比べてどうだったか」が触れられていると、さらに信憑性が増す。
サウンドハウスのレビュー例では「OD-9と比較して中域の出方が自然だった」「EP Boosterと併用している」などのコメントがあり、これがとても参考になった。
✅ 使用期間が書かれているか?
「10年使い続けている」
「購入してすぐの感想」
──こうした情報は意外に重要だ。短期間では見えないこともあるので、長期使用のレビューは説得力がある。
✅ 良い点・悪い点の両方が挙げられているか?
一方的にベタ褒めしているレビューは、ちょっと怪しいこともある。
筆者が特に信用するのは「クランチの出音は最高。ただしノイズがやや多い」「単体では薄いけど他の歪みと重ねると一気に化ける」といった、冷静に長所短所を指摘しているものだ。
逆に注意すべきレビューの特徴
一方で、次のようなレビューはあまり参考ならない。
❌ 不具合報告だけで終わる
「音が出なかった」「スイッチがすぐ壊れた」などは、個体差や初期不良の可能性が高い。こうしたレビューは、機材の音質や特性を判断する材料にはならない。
音が出なかった、すぐ壊れた=製品のせいではない可能性は十分ある。
ただその人の使い方が間違っていただけかもしれない。
❌ 感情的な酷評
「全然使えない」「すぐ売った」など、感情が先走っていて理由が明確でないレビューは注意が必要だ。冷静に書かれた内容と見比べるのが大事。
使いこなせなかった、間違って買ったって人がそのことを認められずに書いてるんだなーと思えば良い。
❌ まだ使っていないのにレビューしている
意外とあるのが「まだ買ってませんが期待して★3」などの投稿。
憶測や推測で「こういう風に使ってみたい、ここはどうなんだろう?」などと書かれているならまだしも、本当に内容が全くないものを投稿してしまう人が結構いる。
なぜこんな投稿をしてしまうのか理解に苦しむが、これも完全にスルーでOKだ。
動画レビューも慎重に見極めよう
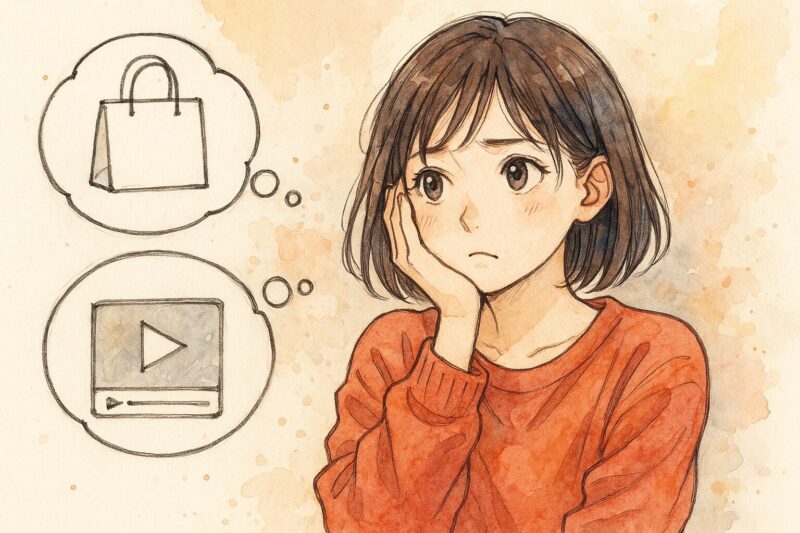
最近は、インフルエンサーや楽器店がYouTubeで機材レビュー動画を出すことも増えてきた。映像と音で確認できるのは便利だが、これも玉石混交であることを忘れてはいけない。
筆者が信頼する基準は次の3つ
✅ 音がクリアでわかりやすい
レビュー動画でまず確認したいのは、音がクリアに録れているかどうかだ。
これは単に録音機材の良し悪しだけでなく、そのレビューアー自身が
「機材の魅力を引き出せる人かどうか」を見極めるポイントでもある。
筆者が信頼しているのは、単に「音が良い」というだけでなく、機材の特徴をきちんと理解して、その魅力を最大限に引き出してくれる人の動画だ。
そういった人は、動画の中でさまざまなセッティングを試してくれることが多い:
EQを変えてどんな音の変化があるか
ゲインを上げ下げしてクリーン~歪みまでの幅を見せてくれる
ピックアップポジションを変えて、反応の違いを聴かせる
こうした丁寧なアプローチは、「自分が買ったときのイメージ」を明確にしてくれる。
逆に、録音環境が悪いのか、またはそもそもレビューアーが機材の特徴を理解していないのか、イマイチな音しか出せない動画も存在する。
そういう動画は、「この機材、実はイマイチなのでは?」と誤解を生む危険があるが、実際は弾き手やセッティングの問題である場合が少なくない。
要するに、レビュー動画の「音が良い」というのは、単なる機材の性能だけでなく、レビューアーの機材理解度と表現力の証明でもある。
だからこそ、音がしっかり作り込まれていて、いろんなセッティングを試して聴かせてくれる動画は、特に信頼できるのだ。
✅ 演奏が上手い
レビュー動画で特に重視しているのが、演奏者のスキルだ。
なぜなら、機材は弾き手の力量によって引き出せる音の幅や魅力が大きく変わるからだ。
筆者が信頼できると感じるのは、ただ単に「上手い人」ではなく、いろいろな奏法やニュアンスを駆使して音を聴かせてくれる人だ。
例えば:
ピッキングの強弱をしっかりつけて弾いてくれる
指弾き、ミュート、ハイブリッドピッキングなど多彩な奏法を交える
ソロフレーズだけでなく、コードストロークやバッキングも聴かせる
クリーンからクランチ、歪みまで幅広く音を試してくれる
──こうした演奏は、機材の表現力の高さやキャラクターの変化がよくわかる。
特にオーバードライブなどニュアンスを拾いやすいエフェクターは、どんな風に弾かれるかで印象がまったく変わるので、この点は非常に重要だ。
逆に、ずっと同じ単音フレーズを繰り返しているだけの動画だと、「その機材がどこまで対応できるのか?」というイメージがつかみにくい。
たとえば「クランチでのバッキングはどんな音?」「ピッキングのニュアンスで歪み方は変わる?」といった疑問が解消されないまま終わってしまうことがある。
さまざまな弾き方で音を引き出してくれる演奏者は、やはり信頼できる情報源だと筆者は感じている。
✅ コメントが独自性を持っている
レビュー動画で筆者が最も重視しているのが、コメントの「独自性」だ。
つまり、その人ならではの使い方の提案や、実際に試して得られたリアルな体験談が語られているかどうか。
特にありがたいのは、例えばこういうコメントだ
「自分ならこういうシチュエーションで使いたい」という具体的な提案
「まずは定番の使い方としてこう設定すると間違いない」というアドバイス
さらに一歩踏み込んで、「あまり知られていないけど、こういう使い方をすると面白い結果が出る」などの新しい視点
こういう情報は、メーカーが用意したカタログやキャッチコピーには載っていないリアルな知見なので、とても参考になる。
逆に、コメントが「ゲインはこうです」「EQはこう効きます」など、メーカーの公式情報の域を超えないものしか出てこないと、筆者は正直「浅いな」と感じてしまう。
そうした動画は、機材そのものをより深く理解しているというより、「とりあえず紹介しているだけ」という印象が強く、あまり信頼しないようにしている。
レビューは、単なる製品説明ではなく、実際に使った人だからこそ見える景色を共有するものだと筆者は思っている。
だからこそ、独自性があり、自分の言葉で語ってくれるレビューは、見ていてもワクワクするし、非常に参考になるのだ。
✅ 菰口雄矢さんのレビューはお手本
ここで筆者が信頼しているレビューアーのひとりを挙げるなら、菰口雄矢さんだ。
彼の機材レビューは、ここまで解説してきた「音の良さ」「演奏の上手さ」「コメントの独自性」という全てを兼ね備えている。
演奏は多彩なニュアンスとフレーズで、その機材のポテンシャルをしっかり引き出してくれる。というか日本トップクラスのギタリストがレビューしてくれるなんて冷静に考えて贅沢過ぎる。
音も録音環境がしっかりしている媒体にキャスティングされている。(デジマート、Limetone Audioなど)
コメントでは、自分なりの使い方の提案や、応用アイデアも含めて語ってくれるので、視聴者が「こう使ってみたい」と想像しやすい。
ただ機材を「紹介する」だけでなく、どう使いこなすか、どう楽しむかまできちんと提示してくれるので、非常に信頼性が高いレビューアーだと筆者は感じている。
上手すぎて参考にならない?は本当?
レビュー動画について、よく耳にする意見が「上手すぎて参考にならない」というものだ。
これは確かに一理あって、「デモンストレーターがプロ級の腕前だと、自分が実際に使ったときに同じ音が出せるわけじゃない」と不安になる人も多いだろう。
筆者もその気持ちはよくわかる。上手い人が弾くと、機材が本来持っている以上に「良く聞こえすぎてしまう」ことがあるのは事実だ。
しかし、それでもやはり筆者は「上手い人のレビューが最も信頼できる」と考えている。
なぜなら、上手いからこそ、その機材の持つ「最高打点」──つまりポテンシャルの限界を見せてくれるからだ。
これは、下手な演奏者には絶対に再現できない部分。逆に、演奏が拙いと機材本来の良さが引き出されず「この機材、全然良くないな」と誤解される危険がある。
「結局いつもの音問題」
もうひとつ、レビュー動画でよくあるのが「デモンストレーターが弾くと、どの機材でも結局その人の“いつもの音”になる」という現象だ。
これも一見「参考になりづらい」と感じることがあるが、筆者はここにも重要なヒントが隠れていると考えている。
その人がどんな機材でも似た音を出しているなら、それはつまり「弾き手の実力を反映させるタイプの機材」だという見方ができる。
逆に、その人が普段と違うニュアンスや音色を出している場合は、「機材のキャラクターが強く、音色を支配しているタイプ」だと判断できる。
また、こうした「いつもの音」が出ている場合、そもそもその機材が繊細な表現を拾えるほど感度が高いからこそ、メーカー側がその演奏者をデモンストレーターとして選んでいる可能性もある。
要は、「誰が弾いても同じ音」になる機材ではなく、「弾き手の色を反映させる高い表現力を持つ機材」だからこそ、その人が起用されている──そう考えるのが自然だ。
結論
「上手すぎて参考にならない」という懸念は理解できるが、結局のところレビューは「機材のポテンシャルを見極める場」でもある。
だからこそ、筆者はこれからも上手い人の演奏・レビューを重視するつもりだ。
自分の演奏力が追いつかない部分があったとしても、「この機材はここまでできる」という上限値を知ることができるのは大きな価値があると感じている。
できれば実機を触って判断を

ここまでレビューや動画の見極め方を解説してきたが、筆者としてはもうひとつ強調しておきたいことがある。
それは、「レビューだけを見て決めるのではなく、最終的には実機を自分で触って判断してほしい」ということだ。
もちろん、これは検討している機材が近隣の楽器店で取り扱われている場合に限るが、やはり実際に触ってみることで、レビューではわからなかった部分が見えてくる。
レビューはあくまで「他人の意見」。
大事なのは、それを参考にしつつも、最終的に「自分の耳と手でどう感じるか?」という主観的な視点だ。
たとえば「ノイズが多い」と書かれていても、実際には自分の環境では全く気にならないこともあるし、逆に「すごく使いやすい」という評判のものが、自分にはしっくりこないこともある。
さらに、楽器店に足を運ぶと思わぬ新しい出会いがあることも多い。
検討している機材以外にも、店員さんが似たモデルやより自分の希望に近い商品を提案してくれることもあり、結果的にもっと良い選択肢にたどり着けるケースもある。
また、中古品コーナーを見てみるのも面白い。新品とは違い、その時その場所にしかない一期一会の出会いがあるのが中古品の魅力だ。
確かに通販は便利で、レビューを見ながら簡単に購入できる時代だが、
やはり地域の楽器店を支えることも大切だと筆者は感じている。
地元の楽器店が元気であれば、地域のミュージシャン同士がつながり、音楽文化そのものが発展していく。
だからこそ、レビューをチェックしたうえで、ぜひ足しげく楽器店に足を運び、リアルな体験を積み重ねてほしい──それが筆者からの心からの願いだ。
Q&Aで記事を振り返り
Q:通販レビューはどこを見れば信頼できる?
A:使用環境(アンプやギターの種類)、ジャンル、他機材との比較、使用期間などが具体的に書かれているレビューは特に参考になる。また、長所と短所の両方を挙げているレビューも信頼性が高い。
Q:レビュー動画は何を重視して見ればいい?
A:音質がクリアで録音環境が整っていること、演奏が上手でニュアンスの違いまでしっかり弾き分けていること、そしてコメントに独自の提案や実体験が含まれていること。この3つがそろっている動画は特に信頼できる。
Q:よく言われる「上手すぎて参考にならない」は本当?
A:確かに上手い人が弾くと機材が実力以上に良く聞こえてしまうことはあるが、逆に下手な演奏では機材のポテンシャルがわからない。上手な人の演奏は機材の「最高打点」を示してくれるので、むしろ参考になる部分が多い。
Q:レビューだけで判断してもいいの?
A:レビューはとても有益な情報源だが、可能であれば最終的には自分で実機を触って判断することが理想的。レビュー内容を参考にしつつ、自分の耳と手で確かめることが最も納得のいく選び方になる。
Q:なぜ実店舗に行くのがおすすめなの?
A:実店舗では、実機を試せるだけでなく、店員さんが似た商品を提案してくれることもある。中古品との思わぬ出会いも魅力のひとつ。また、地域の楽器店を利用することは、地元の音楽環境を守り、発展させることにもつながる。
最後に
今回は、通販サイトのレビューやYouTubeなどの動画レビューを題材に、機材レビューの見極め方を解説してきた。
レビューは、機材選びを助けてくれる強力な味方だが、情報の質は玉石混交。そのため、内容を見極める力がとても大切だ。
さらに、レビューを参考にしながらも、実際に自分の耳と手で確かめる体験の重要性についても触れてきた。楽器店でのリアルな出会いや、スタッフの提案から得られる発見は、レビューだけでは得られない貴重なものだ。
ネットが発達した今でも、最終的な判断をするのは自分自身。だからこそ、他人の意見を参考にしつつも、自分の感覚を信じることが何より大切だと筆者は感じている。
このブログでは今後も、ギターを趣味で楽しんでいる皆さんが、安心して機材選びができるような情報や、日々のギターライフがもっと豊かになるヒントを発信していく予定だ。
ぜひこれからもチェックしてもらえたら嬉しい。
あなたのギターライフがさらに楽しく、充実したものになりますように。