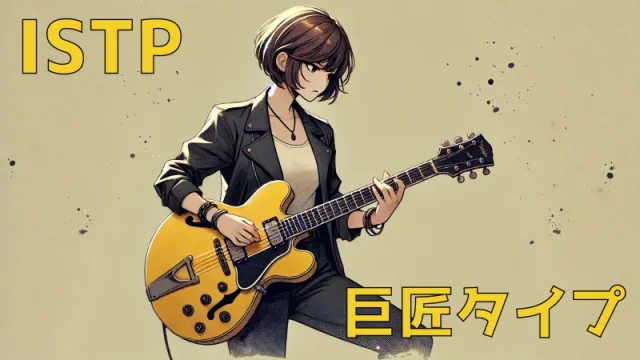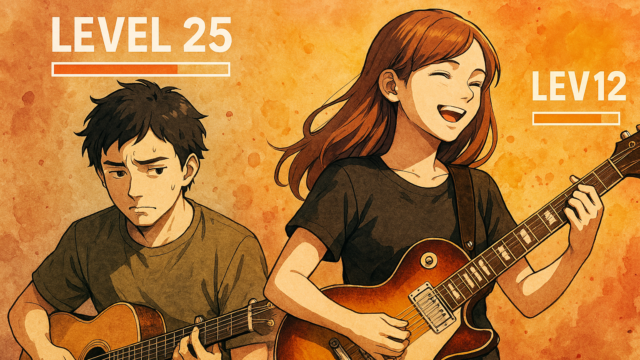個性は、才能ではなくセンスで作られる。蓄積があなたらしさを育てる

「あの人、センスあるよね」
そんなふうに誰かを評する場面は日常の中に溢れている。あるいは、自分にはない感覚に触れて、「センスある人ってやっぱり特別なんだな…」と感じたことがあるかもしれない。
でも、そこでふと立ち止まってみてほしい。
センスって、そもそも才能なのだろうか?
この問いについて、少し掘り下げて考えてみたい。
才能とは何か?──“初期値”としての資質
まず、よく言われる「才能」について簡単に整理してみる。
才能とは、ざっくり言えば次のようなものだろう。
身体的な特徴が、その分野にフィットしていること
人が苦に思うことを、苦とせずにこなせる性質を持っていること
たとえばスポーツなら、身体能力や反射神経。音楽なら、絶対音感や手の柔軟性。あるいは「努力できること自体が才能だ」と言われることもある。
これらは多くの場合、先天的なものに由来している。生まれつき備わっている“初期値”の高さこそが才能である、という考え方だ。
だからこそ、「センスがある人=才能がある人」と、同一視されやすい。
でも、ここに落とし穴がある。実際のところ、“センス”とはまったく別のルートを通って磨かれていることが多いのだ。
センスの正体は“蓄積値”にある
「センスがある」と言われる人たちをよく観察してみると、そこには明確な共通点がある。
それは、リテラシーの高さと、圧倒的なインプット量だ。
たとえば音楽で言えば、流行のヒット曲だけでなく、過去の名曲、海外のジャンル、時代背景まで掘り下げて知っている。しかも、それらを「なんとなく」ではなく、構造や響き、文脈まで分析的に見ている。
スポーツでも、ただ練習しているだけではなく、他国の選手のプレーを研究したり、戦術の歴史を学んでいたりする。
中には、自分の専門外の分野についても驚くほど詳しい人がいる。まるで“趣味の専門家”のように。
そういった人のアウトプットには、自然と深みや文脈がにじみ出る。
「どこかで見たようで、どこにもない」──そんな独特の感覚が生まれるのは、その人が持つ“蓄積”の量と質の違いなのだ。
他ジャンルからの“横流し”こそがセンスの真価
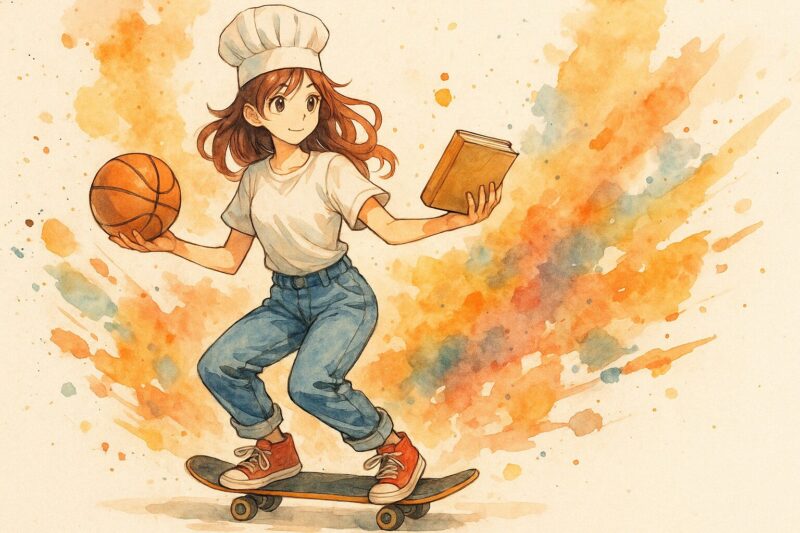
センスの強みは、単に「詳しい」「多く知っている」ということだけではない。
本当の強さは、他ジャンルから得た知識や体験を自分の表現に応用できることにある。
たとえば、ミュージシャンが映画の構成や小説のリズム感からインスピレーションを受けたり、
デザイナーが建築や生物学のパターンをデザインに落とし込んだりする。
こうした「横展開」ができる人は、自分の作品に独自の切り口を与えることができる。
その結果、ただの“上手い”を超えて、「この人ならでは」と思わせる個性が生まれる。
つまり、横展開力こそが、その人らしさ=個性をつくる鍵なのだ。
逆に、専門内だけで完結していると、どこか「浅く」「似たようなもの」になってしまいやすい。
個性は、知識と経験の“にじみ出し”
個性というと、「誰もやってないことをやる」「突拍子もない発想を出す」ことだと思われがちだ。
でも実際には、そういった奇抜さは一過性で終わることが多い。
本当の個性は、知識と経験の蓄積が、意識せずとも表ににじみ出てくるものだ。
無理に「個性を出そう」として出せるものではない。
ただ、自分が本当に面白いと思ったことに夢中になって、それを深く掘っていく。
その積み重ねが、自分でも気づかないうちに“その人らしさ”を形作っていく。
「センスがない」と言い訳する前に
「自分にはセンスがない」
そう言って立ち止まってしまう人は多い。
でも、その言葉を口にした瞬間に、もう一歩も進めなくなってしまう。
センスとは、誰かから与えられるものではない。
無理に背伸びして手に入れるものでもない。
「これ面白い」「もっと知りたい」
そう思ったものに、素直にのめり込んでいくことで、後から“センスある人”として見られるようになるだけだ。
だから、「センスがない」と言ってしまう前に、まずは何かに夢中になってみよう。
センスとは、好奇心の延長線にある
才能は初期値。
センスは蓄積値。
もちろん、先天的な能力でアドバンテージを持つ人はいる。
でも、センスある人の多くは、知識と経験の積み重ねを、自分なりの形でアウトプットしているだけだ。
しかもそれは、分野を越えて“横展開”できるからこそ、その人にしか出せない個性になる。
だから今日から、「面白い」と思ったことに素直になってみよう。
その一歩が、あなたの“センス”を育てる最初の一歩になる。