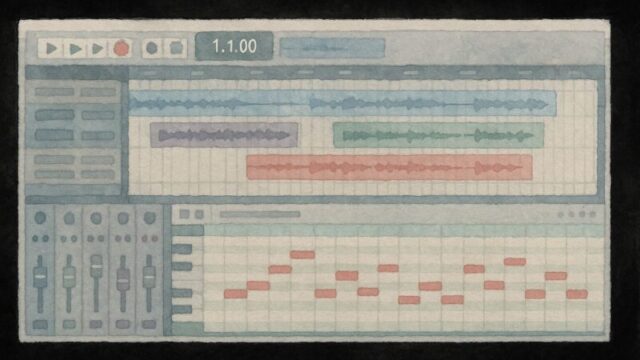作曲アイディアが浮かばない原因と対処法|メモで曲の種を量産する
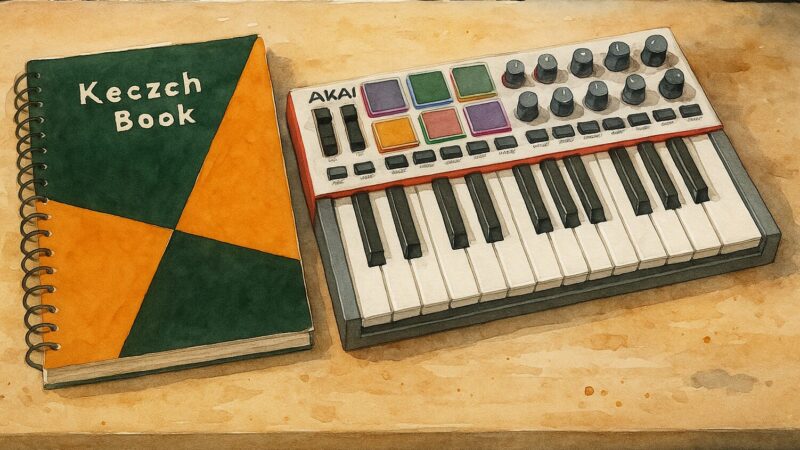
AI時代でも「自分で作りたい欲」は消えない
生成AIによる楽曲は質を上げ続けている。雰囲気や条件をプロンプトに打ち込めば音源が一瞬で作れてしまう。
しかし、それでも自分で音を選び、自分のルールで曲を仕上げたいという欲求は残るはずだ。
では、なぜ多くの人がDTMの前で止まるのか。
理由はシンプルだ。「曲を作りたい」という衝動があっても、素材のストックがないからだ。特に経験が浅い時期は、机に座って考えても前に進みにくい。
その対処法は準備だ。曲の構想・表現したいこと(テーマ)・フレーズ・言葉を日常的に記録し、ネタを集める。
素材が揃えば、DTMは設計と検証のフェーズに切り替わり、曲作りに移行できる。これは地味だが最短ルートだ。
なぜアイディアが浮かばないのか
作曲は“0→1のひらめき”ではなく、“素材→組み合わせ→検証”の工程で進む。
白紙の状態では評価軸が立たない。拍子・テンポ・キー・断片メロ・言葉のどれか一つでもあると、比較と判断が可能になる。
経験が浅いほど、DAW操作=作曲だと誤解しがちだ。
実際は準備7割・実装3割。先に素材を貯めておけば、録音や打ち込みは驚くほど速くなる。
スタートの遅延が消える。完成率が上がる。振り返りも具体化する。
作曲準備の全体設計:4つのメモを溜める
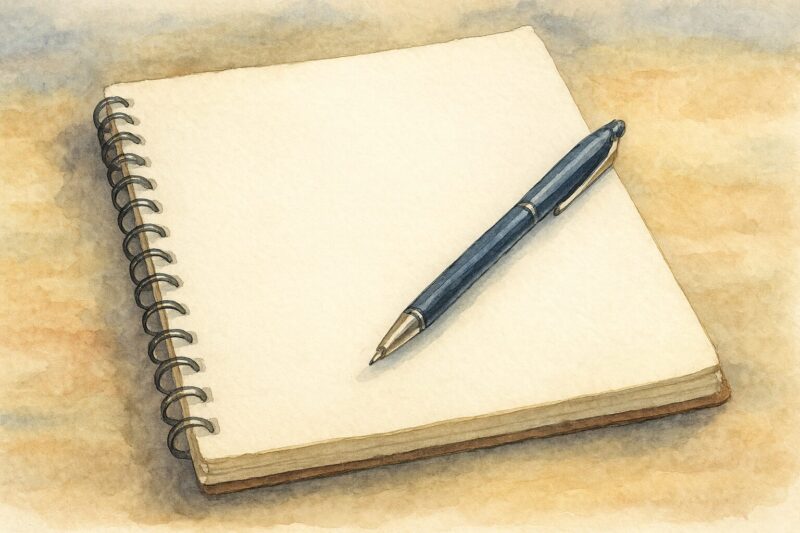
ネタとして機能するカテゴリーを4つほど紹介しよう。
どれも短文・断片でOK。完璧に書こうとしないこと。
1. 曲の構想をメモする(フォームと質感の骨組み)
構想は曲の「地図」だ。開始前に地図があると迷わない。
例)
- 3/4拍子で壮大に。テンポは90前後。
- A-B-サビに頼らない構成。リフを積極的に使う。
- 曲中に2回転調。Bで平行長調、終盤で完全四度上。
拍子/テンポ/想定尺/山と谷(どこで景色を変えるか)/音量設計(静→爆など)
曲の構成に関わる要素で取り入れたいものをメモしていこう。
「3/4・遅め・終盤で一段上げる」とかだけでも十分な下書きになる。
好きなアーティストの楽曲の中で面白い仕掛けをみつけてそれをメモにストックしていくところから始めよう。
2025年リリースの楽曲でいえば、サカナクションの怪獣は面白い仕掛けが満載だ
例)
- Aメロはじまり、印象的なピアノフレーズ、ディレイのフィードバック
- Bメロ、Cメロ、サビとセクションが多い
- 二周目は各メロディの聴かせ方が違う
- 落ちサビで最初のピアノフレーズを挿入
- 最後はBメロのコーラスで締めくくり
てな具合に楽曲の中でどんなアイディアが盛り込まれていたかをメモしておく。
2. 表現したいこと(テーマ)を言語化する
テーマは選択を絞る“制約”だ。制約があるほど創作は速くなる。
例)
- 天才と凡才の残酷さ。
- 大正時代の恋愛。
- 早起きの特別感。
抽象でいい。最初は名詞・短語でOK。「残酷さ」「均衡」「遅れて届く幸せ」など。
映画や漫画などからもテーマの抽出が出来る。
例)
- 漫画ワンピース 自由と支配、正義と悪、真実と嘘の対立構造
- 今敏作品 虚構と現実をあらゆる視点で描いている
- 鬼滅の刃 有限と永遠、生と死、死に抗った鬼と尊厳を守る人間との戦い
など
作品のテーマを抽出してそれをモチーフに楽曲を作るという手法も有効だ。
3. フレーズ(音の断片)を溜める
気に入ったフレーズ、なんとなく作ったリフなんかが曲の骨子になるかもしれない。
例)
- 2小節のギターリフ。
- 4音の歌モチーフ。
- 好きなコード進行(例:| Em | C | G | D |)。
4小節以内の簡単なメモとして録音、単体でMP3などにしておく。
その際にタッピングフレーズ20251015など、大雑把な内容と日付をファイル名にメモしておく事で検索性が増す。
また、印象的なフレーズやリズムで引用できそうなものをピックアップ
例)
- レッドツェッペリンの移民の歌 イントロのリズムパターン
- メタリカのマスターオブパペッツ 曲頭のキメ
- B`zのさまよえる蒼い弾丸などで使われているメジャーコードだけのコード進行 F/G/A/A
これらを拝借したりアレンジする事で曲の取っ掛かりになる。
4. 言葉(タイトル・歌詞の芯)を集める
タイトル案や歌詞からテーマを作る時に役立つ。
例)
- 偉人の名言
- 刺さった歌詞
- 友人の一言
- 漫画のセリフ
- 秀逸なボケやツッコミ
引用元やその言葉が用いられた背景も一緒に書く事でその時の意味を辿れる。
文章ではなく短いワードの方が良い。そのほうが解釈の幅が広がる。
楽曲のアイディアとしては使えないなと決めつけず、日常のやりとりだから共感できることも。
例)
- おならで返事しないでくれる?
- Wi-Fiに避けられてる気がする
- 朝を迎える事だけは得意。目を瞑ってても余裕。
- など、作曲に限らずいつか役に立つ可能性があるので取りあえずメモしておくのはおすすめ。
メモを“曲”に変える運用法
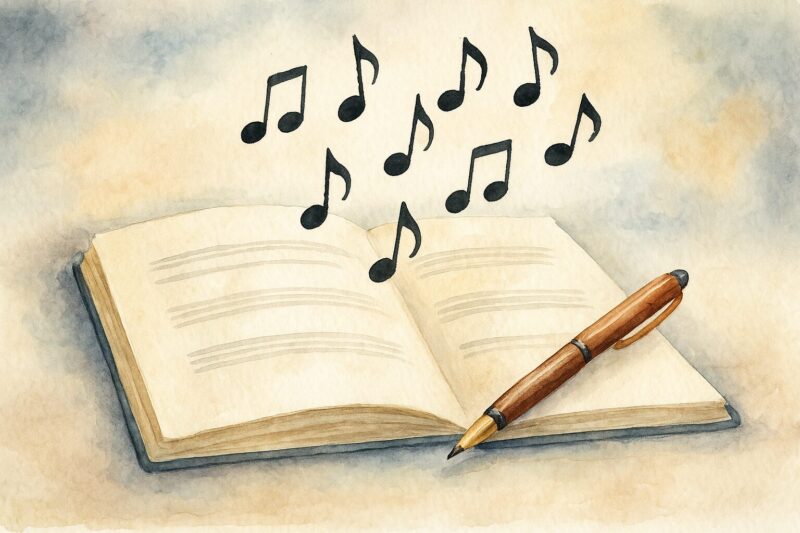
断片的なメモを眺めながらアイディア出しをしていく。
組み合わせ:3枚引き+クラスタリングで骨組みを作る
複数のメモを組み合わせることでより具体的なのイ用に落とし込む。
ワード+楽曲のルール
例)
雨の日+軽快な6/8拍子+コード進行[AM7/G#7/C#m7/EM7]
その上でそこから連想させるワードを肉付けしていく
例)
長靴、水たまり、切なさ
この工程を経る事で拍子やkeyなどの楽曲のルールと表現するテーマが決まり、作業を始めやすくなる。
反転:意味・時間・役割を裏返してドラマを作る
メモのワードを変形させることでアイディアを出す。
意味の反転:言葉・テーマの逆義語を1行添える。
例)
「雨の日落ち着く」↔「雨の日は憂鬱」
時間の反転:朝/夜、往路/復路など時間軸を入れ替える。
例)
A=雨上がり、虹 ↔ B=降り出し、ゲリラ豪雨
役割の反転:主役/伴奏、メロ/リフを入れ替える。
例)
ギターリフとメロディーが交互に強調される。
視点変更:語り手・距離・スケールをずらす
観測位置をずらす事でワードの持つ世界を広げる。
語り手:一人称→三人称/観察者視点へ。人物A↔人物B
距離:クローズアップ(質感重視)大粒の雨↔ ロング(情景重視)ずぶ濡れの街
スケール:個の感情「憂鬱」↔街・季節「梅雨」などマクロへ。
マインドマップを使う
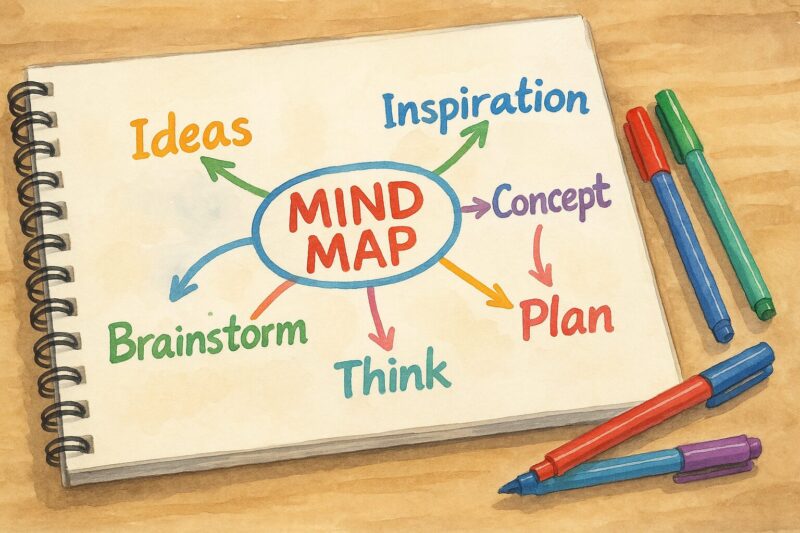
「ひとつのメモ」から複数の曲の“種”を量産する。思考停止を避け、視点の切り替えと連想の深掘りでテーマ→構成→フレーズまで落とし込む。
マインドマップの概要
定義:中央にテーマ(親ノード)を書き、放射状に連想語(子ノード)を広げる思考法。
効く理由
視覚的に広がりと関係性が見える→抜け漏れが減る。
“遠い連想”まで辿れる→意外性が出る。
クラスターごとに曲の方向性を立てやすい。
作曲でのゴール:単語の木を、リズム/ハーモニー/音色/構成の四要素に翻訳すること。
↓参考書籍
例題:「雨の日」をテーマにアイデアを出す(連想→派生)
中央に「雨の日」。そこから思いつく語を否定せずに出す。さらに各語から2階層以上、連想を伸ばす。
├─ 水たまり
│ ├─ 長靴
│ └─ 跳ねる/波紋
├─ 傘
│ ├─ 忘れがち
│ ├─ ビニール傘の質感
│ └─ 共有(相合い傘/置き傘)
├─ カエル
│ ├─ 両生類
│ ├─ 鳴き声=リズムパターン
│ └─ 田んぼ/土の匂い
└─ 雨音
├─ ホワイトノイズ
├─ 屋根を叩く粒の大小
└─ 窓ガラスの伝い方(不規則)
ポイント
名詞・動詞・質感語を混ぜる(例:波紋/忘れがち/ホワイトノイズ)。
同じ語から相反する視点も足す(例:傘=守る/傘=邪魔)。
3〜5分で数を最優先。正しさは後で考える。
連想を“音”に翻訳する
マインドマップの枝ごとに、音楽パラメータへ変換する。
難しそうに見えるかもしれないが率直に自分が感じたことをもとに音楽表現に変換していこう。
先ほどのマインドマップの語を使ってどのように翻訳できるか見ていこう。
1) リズムへの翻訳
語感や現象をリズムへ解釈する。
水たまり→波紋:付点音符やディレイトリックで円が広がる感じを作る。
カエル→鳴き声:シンコペーションや2対3のポリリズムで不規則な呼応を表現。
傘→ビニール傘の質感:「バッと傘を開く」などの歌詞に合わせてキメを作る。
雨音→ホワイトノイズ:ハイハットでトラップやドランクビート的な揺らぎを演出。
2) ハーモニーへの翻訳
コードで曲の展開をコントロール、表現する。
波紋:コードに9th/11thを足して“広がり”を作る。
相合い傘:平行長調/短調を行き来。二人の距離感を和声で表現。
両生類:モーダルインターチェンジで水と陸の行き来を表現。
忘れがち:sus4で一抹の不安を残しつつサビ頭で解決させる構成。
3) 音色・質感への翻訳
音色の翻訳が一番やりやすいかもしれない。
ビニール傘の質感:薄いシンセパッド。
屋根を叩く粒の大小:レインSFXをレイヤー。
窓ガラスの不規則:グラニュラーでピッチを微細に揺らす。
4) 構成への翻訳
序盤:遠くの雨=浮遊感のあるコード進行。
中盤:傘を開く=キメを使いつつポリリズム、奇数拍子などで雨音の不規則性、ビッグマフでゲリラ豪雨的な轟音を表現。
終盤:止み際=メロディはそのままに前向きなコード進行に変更し着地。
このように言葉をもとに表現していく事で表現の幅や楽曲の分析力を向上させる事が出来る。
古いメモを捨てない
文脈が変わると解釈も変わる。去年に見たメモが今見ると別の解釈を生む事もある。
再度メモを見るまでに消化したコンテンツや日々の気づき、経験が蓄積されることで感じ方に変化が起こる。
メモを捨てずにとりあえず取っておくと後々の作品に生きていくこともある。
↓メモは無地のノートがおすすめ
↓マインドマップは大判のスケッチブックにカラーのマッキ―で書くとより多くのアイディアが出せるのでおすすめ。
作曲の手法とテーマの関係
テクニックは重要だが、作品に重みを与えるのはやはりテーマだ。
先にテーマが定まると、やることとやらないことが自然に選別される。
選択肢が削られ、判断が速くなり、結果として音色や進行、構成に統一感が生まれる。
迷いながら技法を足していくより、最初に意味を据えてから技術を呼び込む方が完成までの道筋は短くなる。
まとめ|作曲は“準備”で8割決まる
AIがどれだけ進化しても、「自分で作りたい欲」は消えない。
手が止まる原因はひらめき不足ではなく、素材不足だ。
構想・テーマ・フレーズ・言葉の4分類で日々ストックし、
組み合わせ→反転→視点変更→マインドマップ→音への翻訳という流れに載せれば、DTMは設計と検証に集中できる。
白紙で悩む時間は削れ、完成率は上がる。
テーマを先に立てることで選択肢は自然に絞られ、判断は速くなり、統一感が生まれる。技術はその枠の中でこそ活きる。
スマホのメモアプリでも問題ないので自身の興味関心を記録する癖をつけよう。
最後に
作曲は“ひらめき待ち”ではなく、“準備→編集”の反復だ。
小さな断片を毎日積み上げていき、短時間で検証し続ける。
これだけで、机の前で停止する時間が減るだろう。