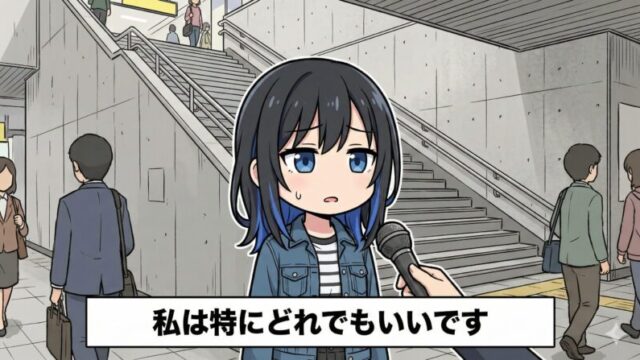音楽理論は必要?不要?ギタリストの視点で理論の本当の価値を考える

「音楽理論って結局、必要なの?」
ギターを弾いていると、一度は誰でも考えるテーマだと思う。SNSやYouTubeでもよく議論になっていて、
「感覚だけで十分」「理論がないと詰む」など、極端な意見も多く見かける。
ただ、実際のところ理論が必要かどうかは、プレイスタイルや目的によって全く違う。
結論から言えば、“理論を知らなくても音楽はできる”。けれど、“理論を知っていた方が圧倒的に便利な場面が増える”というのも事実だ。
そしてもう一歩踏み込んで言えば、自己完結で楽しむ趣味のギターが、誰かとの共演や共有に発展した瞬間、理論や譜面の価値は一気に跳ね上がる。それが現場のリアルだ。
理論がなくてもギターは楽しめる。
まず前提として、音楽理論がなくてもギターは弾けるし、曲も作れる。それは間違いない。
実際、名だたるアーティストの中にも「理論はわからない」という人はたくさんいる。
耳と感覚で弾いて、コードやメロディを探りながら音楽を作る──それも立派な表現方法だ。
ただし、それは“個人プレイ”として楽しむ場合に限る。
バンドをやってみたい、他の人と合わせて演奏したい、自分の曲を誰かに伝えたいという段階に進んだ瞬間、
「理論知らないとちょっと不便かも」と感じる場面が確実に出てくる。
読譜力は「練習効率」を大幅にアップさせる武器になる
「譜面って読めたほうがいいの?」という疑問に対して、答えは明確に「YES」だ。
特に独学で練習している人ほど、読譜力の有無で上達スピードに差が出る。
たとえば次のようなシーンを想像してほしい。
TAB譜だけだとリズムがわからず、動画頼りの練習になる
ちょっとテンポが複雑なフレーズになると耳コピで限界がくる
コピーしたい曲が五線譜のみで提供されていて、手が出せない
こうした問題は、簡単な読譜スキルがあるだけで一気に解消される。
特にリズム譜と構成譜が追えるようになると、1曲仕上げるまでの時間も労力もグッと減る。
“譜面が読める”ということは、“音楽の地図が読める”ということ。
道に迷わずに目的地に辿り着けるようになるのだ。
耳コピ=かっこいい?それは少し誤解かもしれない
「耳コピこそ正義」「譜面なんて見ない方が音感が鍛えられる」
そんな風潮も一部にはある。もちろん耳コピは大事なスキルだし、鍛えて損はない。
でも、それが“譜面を使うのは甘え”という意見になるとしたら、ちょっともったいない**。
実際のところ、耳コピと読譜は補完し合う関係にある。
譜面があれば耳コピの確認ができるし、耳で感じた違和感を譜面で修正できる。
何より、耳コピで済むような曲ばかりじゃないというのが現実だ。
微妙なリズムのニュアンスや、構成の細かい変化、拍子のズレなどは、譜面なしでは確認しにくい。
耳も、目も、両方使える状態が一番強い。
「耳コピor読譜」ではなく「耳コピ×読譜」の発想が、練習効率のカギになる。
曲は理論なしでも作れる。でも共有するなら“譜面”が必要になる

これもよくある誤解のひとつが、
「理論なんてなくても名曲は作れる」という話。これは確かにそう。名曲は理論からではなく感情やアイデアから生まれる。
でも──
その“名曲”を誰かに伝えるとき、理論や譜面がないと苦労する。
たとえばバンドでこういうやり取りをしたとしよう。
「AメロはC→G→Am→Fで、サビはちょっとテンポ上がるけど、構成は…んーと、えっと…」
…伝わらない。伝えたいのに、伝えきれない。これは地味にしんどい。
でも譜面があれば、
コード進行
構成
小節数
リズムの位置
がひと目で共有できる。デモ音源+譜面が揃っているだけで、リハーサルは激的にスムーズになる。
つまり、理論や譜面は“共有のための道具”でもある。
「自分だけで作って完結」で終わるか、「人に伝わって初めて完成」なのか──
それによって必要なスキルは変わってくる。
アンサンブルをするなら最低限の“共通言語”は必要
音楽は言語であり、譜面はその文法だ。
アンサンブルは“会話”と同じだから、共通言語がなければ伝達が難しくなる。
特にバンド練やセッションで多いのが、次のような場面:
「4小節目でブレイクして、6拍子に戻るからね」
「Cメロの頭、2拍裏から入るから意識して」
「キー変わるから転調のとこマークしておいて」
これ、譜面が読めれば一瞬で済むやりとりだ。
逆に、読めないと感覚と口頭説明だけで延々とやり取りする羽目になる。
バンドでギターを弾く=音楽的なコミュニケーション能力が求められる
と言い換えてもいい。それを支えるのが、譜面力と最低限の理論知識だ。
「プロでも譜面読めない」って本当?実はレベルが違うだけ

よく「有名ミュージシャンも譜面読めないって言ってた!」という話を耳にする。
確かにそういうインタビューも存在する。
でも注意したいのは、“読めない”の基準が我々とは違うということ。
プロが言う“読めない”は、「クラシック並みの初見は無理」とか「完璧に書き起こしはできない」というレベルの話だったりする。
実際には、構成譜や簡単なリズム譜は普通に扱っていることが多い。
「プロでも読めないんだから、自分も読めなくてOK」と安心するのはちょっと早い。
最低限の譜面力は、むしろ“プロじゃない人”こそ必要な道具だったりする。
結論|理論と譜面力は“義務”じゃない。でも“無いと困る時が必ず来る”
ギターは感覚だけでも楽しめる
でも読譜力があると練習も効率化できる
耳コピは大事。でも譜面も大事
曲作りは自由。でも共有には理論や譜面があると便利
自己完結で満足できなくなった瞬間、譜面力の価値が跳ね上がる
音楽理論や譜面力は、知っていると“選べる道具”が増える。
義務じゃない。けれど、持っていることで行動の自由度が一気に広がる。
今すぐガチで学ぶ必要はない。
でも、「いずれ必要になるかも」と思って、ちょっとずつでも取り入れておくと、未来の自分がラクになる。
とりあえず、構成譜が読めるようになることから始めてみよう。
バンドをやってみたい、曲を共有したい、もっと上達したい──そんな気持ちが出てきたとき、
あなたを助けてくれる“共通言語”になるはずだ。