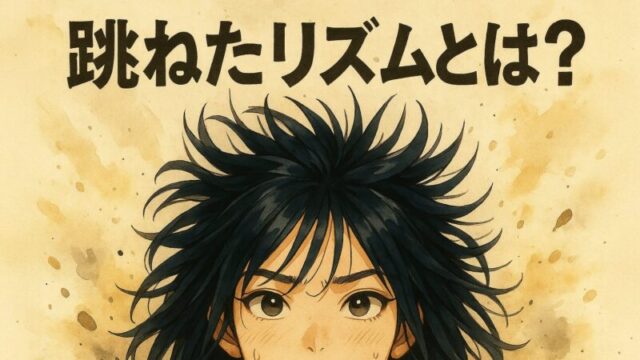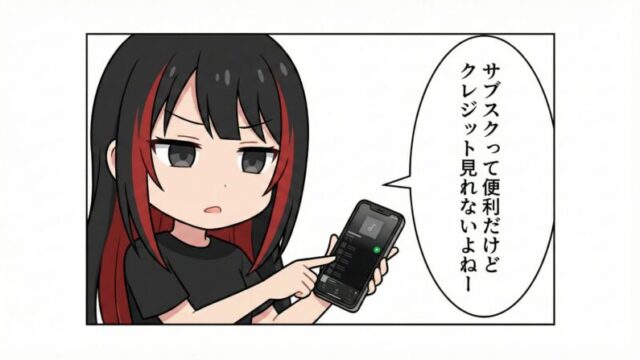J-POPで見るラブソングの歴史――音楽に映る、恋愛のかたちの変化とは?

恋愛って、時代によってこんなにも違うの?
昔のラブソングを聴いていると、「こんな恋、今じゃもうできないな」と感じることがある。きっと、あなたも一度は思ったことがあるはず。
でも、それはおかしなことじゃない。
恋愛は、人と人の関係。そして人の価値観や生活は、時代に左右されるもの。
だから音楽も、時代ごとの“恋のかたち”をしっかりと映し出している。
この記事では、1970年代から2020年代まで、日本のポピュラーミュージックを通して恋愛文化がどう移り変わってきたのかを、リアルに追っていく。
古い曲がなんだか沁みる理由。今のラブソングにどこか冷たさを感じる理由。
その背景にある“恋愛の進化”を、音楽とともに辿ってみよう。
【1970年代】別れは“破局”じゃなく“旅立ち”だった時代の恋愛ソング

恋愛結婚がようやく一般化し始めた頃。
それでもまだ、お見合いや親が決めた許嫁といった制度の名残が色濃く残っていた。
そんな時代の恋愛は、“愛しているのに別れる”ことが多かった。理由は破局ではない。夢や仕事、家族の事情で離れ離れになる。そうせざるを得なかった。
チューリップの「心の旅」、かぐや姫の「神田川」、イルカの「なごり雪」など、70年代の名曲たちは、愛し合っていた二人が環境によって別れを選ばされる物語を描いていた。
恋愛は“報われるもの”ではなかった。
でも、それでも人は人を想った。その切なさが、今も多くの心を打ち続けている。
【1980年代】恋愛は“娯楽”だったーー華やかなバブル時代の恋

日本がバブル景気に沸いた80年代、恋愛は一気に“エンタメ”として花開く。
街にはネオンが溢れ、ディズニーランドが開園し、アイドルが“恋愛の理想像”を提示するようになった。
恋は夢であり、商品であり、イベントだった。
レベッカの「フレンズ」やC-C-Bの「Romanticが止まらない」、米米CLUBの「浪漫飛行」は、現実から少し浮いた、ロマンチックでカラフルな恋を描いている。
恋をすることが、人生を彩る最高のスパイスだった時代。
“リアル”より“理想”に心を委ねることで、恋は特別なものとして成立していた。
【1990年代】恋の“スタイル”に憧れたーー物語としての恋愛

90年代、日本はカルチャーの百花繚乱期に突入する。CDはミリオン連発、ゲーム機戦争、原宿ストリート文化などが交差する中、恋愛も“当たり前”のものとなった。
そして人々は、「どう恋するか」に価値を見出し始める。
小田和正の「ラブ・ストーリーは突然に」は、何気ない日常に訪れる恋のドラマを。
DREAMS COME TRUEの「未来予想図II」は、理想的なカップル像を。
広瀬香美の「ロマンスの神様」は、恋を明るく元気に楽しむ“恋愛アクティブ時代”を象徴した。
恋は人生の必須科目であり、スタイルだった。
“私たち、今、恋してるよね”と思わせてくれる音楽に、人々は熱狂した。
【2000年代】携帯が変えた恋のかたちーー距離が不安を育てる

携帯電話の普及により、恋愛の在り方が劇的に変わったのが2000年代。
メール文化が広がり、「付き合う前のやりとり」が恋愛の中心になる。
どんな内容を送る?どれくらい待つ?返信が来ない理由は?
そんな細かいやり取りに、一喜一憂するのが楽しかった。
YUIの「CHE.R.RY」、絢香の「三日月」、大塚愛の「プラネタリウム」など、物理的距離と心理的距離が恋愛のテーマとなっていく。
ポルノグラフィティの「サウダージ」では、失恋に伴う心理描写を劇的に描くことで普遍的な共感を得た。
成就していない、成就しない、会えない、寂しい、が主役の時代だった。
恋はますます曖昧になり、同時に繊細になっていった。
会えないことが不安で、でもその不安さえも愛しい。
そんな“液晶越しの恋”が主流となる時代だった。
【2010年代】リアルな恋に疲れ、ネットと偶像に逃げた時代
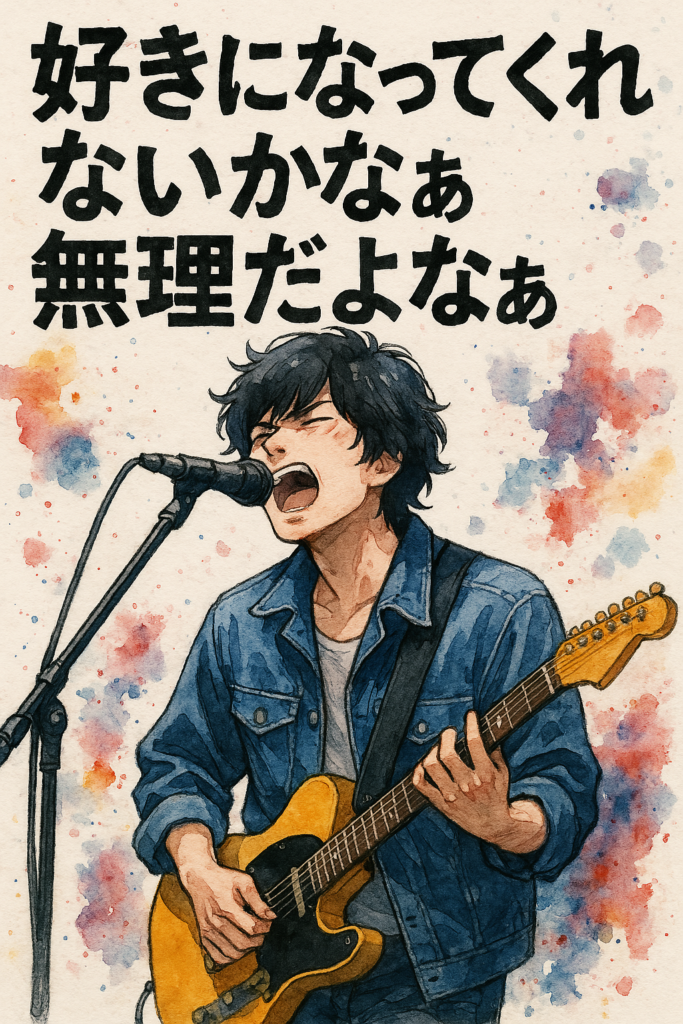
CDランキングを見渡せば、上から下までアイドルグループの名前ばかり。
ジャニーズ、AKB48――
“リアルな恋はもう無理ゲーじゃん”という感情を抱いた若者たちは、偶像に恋をすることでバランスを保っていた。
同時に、音楽の現場はネットに移る。ニコニコ動画ではボカロPたちが本音をぶちまけるように楽曲を投下し、恋愛に対する生々しい本音や傷が、匿名性の中で共有されていった。
西野カナの「会いたくて会いたくて」、ゴールデンボンバーの「女々しくて」、back numberの「高嶺の花子さん」など、恋に負けること、愛されないことが“スタンダード”として歌われた。
もはや、恋は“憧れ”ではなく、“敗北を前提としたもの”だった。
それでも、恋する気持ちは消えなかった。
だからこそ、アイドルとネットという“二つの虚構”が支えになった。
【現代】恋は幻想になったーー性も愛も曖昧な時代
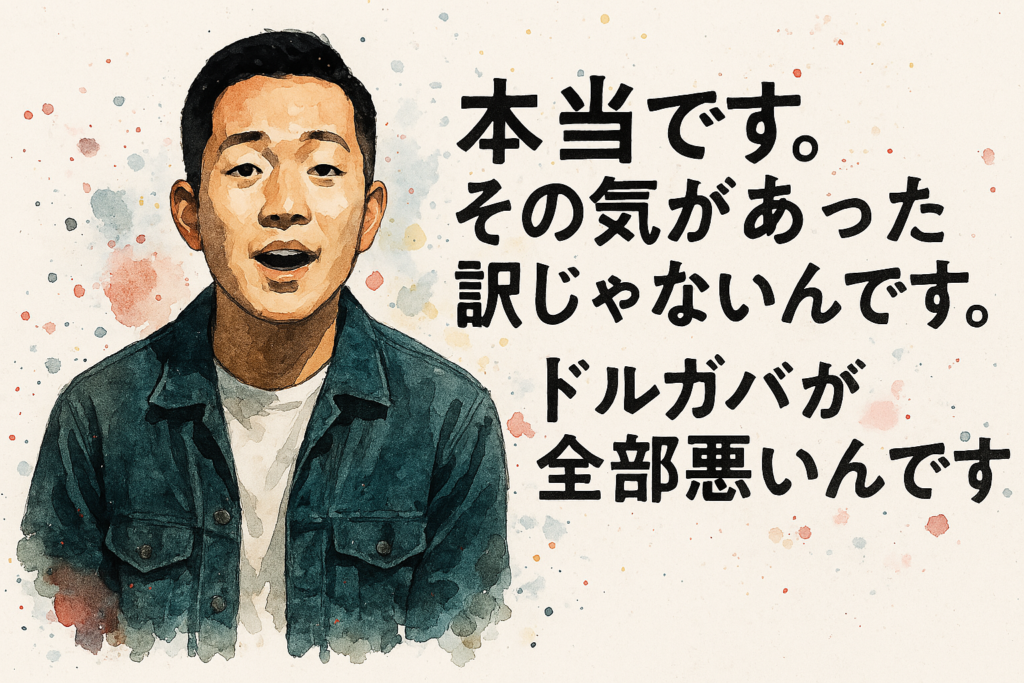 少子化、未婚化、恋愛経験のない大人の増加。
少子化、未婚化、恋愛経験のない大人の増加。
一方で、“恋愛サービス”と呼ばれる形でパパ活、港区女子、レンタル彼女が成立する時代。
恋はとうとう幻想となり、その空洞にお金や欲望が入り込むようになった。
性もまた、曖昧になった。LGBTQ+への理解が進む一方で、“性別に興味を持つこと”そのものがタブー視される空気も出てきた。
恋愛において不可欠だったはずの“性”は、語られにくくなり、恋はますます抽象的に。
Official髭男dismの「Pretender」、あいみょんの「愛を伝えたいだとか」、優里の「ドライフラワー」、瑛人の「香水」、DISH//の「猫」など、多くのヒット曲が“割り切れない気持ち”を歌っている。
愛したいけど、愛せない。愛されたいけど、信じられない。
恋は、ただのオプションになった。
恋愛ソングで振り返る、日本の恋愛文化の移ろい
音楽は、時代の風俗の写し鏡だ。
社会の空気感や価値観の変化は、恋愛ソングにも確かに映り込んでいる。
だからこそ、その時代のラブソングをただ“懐かしむ”だけでなく、背景と一緒に味わってみると、より深くその魅力が見えてくる。
1970年代は、人生に翻弄されながらも真っ直ぐに愛し合い、別れた時代。
1980年代は、恋愛が最高のエンタメとして消費され、華やかさを競った。
1990年代には、恋のスタイルそのものに憧れを抱くようになり、物語としての恋愛が脚光を浴びた。
2000年代には、携帯の登場で“想いのやりとり”が恋愛の主戦場となり、遠距離や片思いが主役になった。
2010年代には、恋が“現実離れ”していき、アイドルとネットの中にその代替を見出す若者たちが現れた。
そして現代。恋愛は幻想となり、コスパで語られ、性すらも曖昧になる。
それでも、恋を描いた歌は消えていない。いや、むしろ今だからこそ、“恋を歌う意味”が問われているのかもしれない。
ここで綴ったのは、あくまで筆者なりの視点に過ぎない。
恋愛の形は、人の数だけあるし、音楽の解釈もまた無限だ。
だけど、こうして時代ごとのラブソングを並べて見ていくと、そこには確かに“日本人の恋の歴史”が浮かび上がってくる。
恋をしていたあの頃の自分。
恋に疲れていた時代の空気。
あるいはまだ見ぬ誰かとの未来。
音楽を通じて、時代の文化を見つめ直してみるのも、なかなかに面白い。