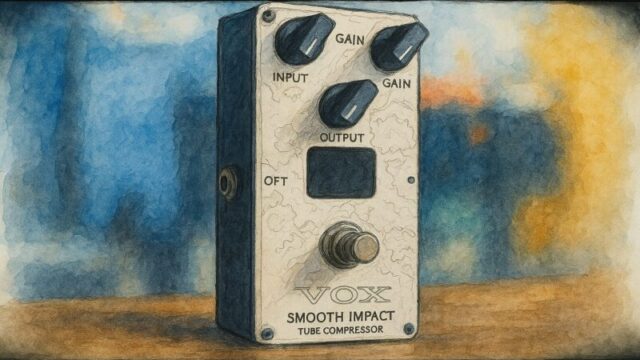なぜギタリストは黒い服を選ぶのか?──ファッションに宿る音の哲学

ライブ会場やSNSでギタリストの姿を見ると、気づくことがある。やたらと“黒い服”が多いのだ。
黒Tに黒パンツ、黒いスニーカー。まるで制服のように、ステージの上では黒が支配的だ。
「ギタリストって黒好きだよね」
そんな言葉で片づけられがちだが、そこにはもっと深い理由がある。
ただのオシャレでも流行でもなく、黒を選ぶことそのものがギタリストとしてのスタンスを表している。
本記事では、ギタリストと“黒”の関係について、実用性・心理・音楽ジャンル・美学・そして例外的な選択肢まで、立体的に掘り下げていく。
黒を選ぶ実用的な理由──現場を支える“戦闘服”
ギタリストにとって、ステージは戦場だ。照明、熱気、汗、飲み物、ケーブル…すべてが絡みつく過酷な現場。
そこで頼りになるのが「黒」だ。
黒は汚れを隠す“プロ仕様の色”
ライブでは汗が吹き出し、飲み物が飛び、ギターからのフィードバックで全身が振動する。
そんな状況で明るい色の服を着ていたら、すぐに汚れが目立ってしまう。
黒なら、その点は圧倒的に有利だ。
ステージ映えする「目立たなさ」
意外かもしれないが、ステージ上では“目立たないこと”が目立つこともある。
派手な照明に照らされる中、黒い服は光を吸収し、ギターや手元が浮き上がる。
つまり黒は、「自分」ではなく「音」や「演奏」を際立たせるための選択なのだ。
コーデに悩まなくて済む「黒は万能」
毎回のライブや撮影で、コーディネートを考えるのは意外と大変。
黒はどんなギターにも合い、トップス・ボトムスの組み合わせにも迷いがない。
時間とエネルギーを音楽に集中させるための、効率的な選択でもある。
性格と心理から見る“黒”──内向的なギタリストにとっての防御色
黒はただの色ではない。
それは“気配を消す”色であり、ギタリストの心情と密接に結びついている。
ギタリスト=内向型が多いという事実
ギターという楽器は、ステージで目立つ一方で、非常に内省的な側面も持つ。
誰かと会話するより、自室で音を作っていたい。そういうタイプは意外と多い。
黒はそんな内向的な人にとって、「自分を守る色」なのだ。
自分より“音”を聴いてほしいという気持ち
黒を身にまとうことで、視覚的な自己主張を抑え、聴衆の意識を音に向けさせる。
それは、「聴いてくれ、自分じゃなくて、ギターの音を」という無言の訴えだ。
音楽ジャンルと黒の親和性──黒が支配する世界観
特定のジャンルでは、黒はもはやファッションというより文化の一部になっている。
そのジャンルの持つ“世界観”を象徴する色でもある。
メタルやプログレはなぜ全身黒なのか?

メタリカ、スリップノット、ピンク・フロイド……彼らは全身を黒で統一することで、
音楽そのものを“視覚化”している。
暗く、重く、哲学的で、時に破壊的──そんな音には、黒が最もよく似合う。
「世界観第一主義」という思想
彼らに共通しているのは、“個”よりも“作品”を前に出す姿勢。
衣装の色が統一されているのは、その象徴だ。
黒は一人ひとりの個性を消し、バンド全体で一つの世界を構築するための色なのだ。
ギターと黒の相性──楽器を引き立てる“背景色”としての黒
エレキギターは、それ自体が非常にファッショナブルな存在。
だからこそ、服装が黒であることに意味がある。
黒はギターを際立たせる“舞台装置”
ギターは個性的なデザインやカラーが多い。赤、青、サンバースト、ナチュラル…。
黒い衣装はそれらを邪魔せず、むしろ際立たせる役割を果たす。
ギターの本数が多いときこそ“黒”が生きる
ライブ中に複数のギターを持ち替えるギタリストも多い。
その際、衣装が黒で統一されていれば、どのギターでもサマになる。
これも黒が“汎用性の高い色”として選ばれる理由だ。
色が持つ意味と“世界観”──黒は何を語り、何を隠すのか
ファッションとは、音楽の“言葉にならない部分”を伝える手段でもある。
ステージ衣装の色は、そのアーティストがどんな世界観を届けたいかによって変わる。
黒が選ばれる理由には、色彩が持つ心理的な意味も深く関わっている。
黒と白は“フォーマル”である
黒はただの地味な色ではない。正装の色でもある。
タキシード、礼服、スーツ──いずれも黒か白を基調としている。
つまり、ギタリストが黒を着るというのは、ライブという“儀式”に挑む覚悟の表れでもある。
カジュアルさを排除し、音に対して“真摯である”という意思表示ともいえる。
それは、「気軽に音楽やってます」ではなく、「表現に命を懸けている」というスタンスだ。




色が入るほど“ポップ”になる
逆に、原色やパステルカラーなどを取り入れると、視覚的に“軽さ”や“楽しさ”が加わる。
これはポップスやファンク、シティポップなど、明るく開けた世界観と相性がいい。
赤やオレンジ → 情熱、躍動感、エネルギー
青や水色 → 爽やかさ、青春、クールさ
紫 → ミステリアス、怪しさ、浮遊感
ピンクや黄色 → 可愛さ、親しみやすさ、遊び心
こうした色を使うアーティストは、音楽以外でも感情や空気感を伝えたいという意図が見える。
ダークな世界観を誘う色はやはり黒
逆に、沈んだ感情や深い内面を表現したいアーティストにとって、黒は最適な色だ。
それは、悲しみや怒り、虚無といった感情を言葉ではなく“装い”で届ける手段となる。
ステージ上で黒に包まれたギタリストが、ゆっくりとコードを鳴らす姿。
それは観客を“内面の世界”へと誘い込む、音と視覚のコラボレーションでもある。
あえて黒を避けるギタリストたち──差別化と表現の自由
ここまで黒のメリットを語ってきたが、あえて黒を選ばないギタリストもいる。
その理由は一つ──「差別化」である。
黒以外を着れば、それだけで目立てる

たとえば、ジョン・メイヤーはシンプルな白Tやカラフルなパーカーで柔らかさを演出する。
Charも白い衣装を着ている印象がある。
周囲が黒ばかりだからこそ、色での個性が際立つのだ。
体型との相性を考えた選択
黒=細く見える、というのは一般的な考え方だが、実際にはタイトな黒ほど体型が浮き彫りになることもある。
ふくよかな体型のギタリストにとっては、明るい色やゆったりした素材の方が“馴染む”場合もある。
フロントマンは黒一色では物足りない──主役に求められる“視覚表現”
ギタリストがバンドの前に立つ、あるいはソロで活動するとなると、事情は変わる。
視線を集めるなら「黒+何か」が必要
全身黒は引き算の美学だが、それだけでは主役の輝きが出ないこともある。
だから、アクセサリーや柄、素材感などで“足し算”をするギタリストが多い。
Lenny Kravitzや布袋寅泰のように、「黒をベースに個性を出す」スタイルが強い。




アコースティックギターと色の親和性──自然な音には“温かさ”が似合う
アコースティックの世界では、黒はやや浮いてしまう場合もある。
木の質感と調和する、ベージュや生成り
アコギは自然な音色と木のぬくもりが魅力だ。
その質感に合うのは、ナチュラルカラーの服。
ベージュ、カーキ、くすみ系ブルーなど、視覚的にも温度を感じさせる色合いが好まれる傾向がある。
黒が“安心”になっていないか──装いもまた表現であるということ
ここまで見てきたように、ギタリストが黒を選ぶ理由には多くの意味がある。
だが、だからこそ気をつけておきたいことがある。
黒を選ぶことが“惰性”になっていないか?
黒は万能だ。合わせやすく、汚れに強く、カッコよく見える。
けれど、それに慣れすぎて「とりあえず黒」になってしまっていないだろうか?
ギターの音が進化しているのに、服装はずっと同じ──
それでは、表現が半分になってしまう。
音楽のジャンル、曲の世界観、自分が届けたい感情。
それらに今の自分の装いは合っているか?
立ち止まって見直すことも、表現者として必要なのではないか。
音だけで勝負できる時代は終わった
SNSが普及し、視覚が音楽の一部になった今。
ギタリストはただ“弾くだけの存在”ではなく、“見られる存在”でもある。
服装もまた演出であり、表現のひとつ。
どんな音を鳴らすかと同じくらい、どんな自分を“魅せる”かが問われている。
ステージに立つということは、自分という作品を観客に差し出すということだ。
黒が自分の音楽を支える色であれば、これからも堂々と着ればいい。
でも、もし「惰性」で着ているのなら、一度だけ立ち止まってほしい。
黒は、あまりにも馴染みやすい色だからこそ、思考停止に陥りやすい色でもあるのだから。
黒はギタリストの“無言の主張”である
黒は、単なる“無難な色”ではない。
むしろ、あらゆる意味で「主張しないことを主張する」色だ。
ギタリストが黒を選ぶのは、自分の音を際立たせたいから。
世界観に溶け込むため。
ギターを引き立てたいから。
そして時に、自分を隠したいから──。
しかしその一方で、あえて黒を避けることで、逆に“自分”を強調するギタリストもいる。
どちらにせよ、黒という色を選ぶか否かは、ギタリストの哲学の表れなのだ。
あなたが次にライブで見るギタリストの服装。その“色”には、きっと音と同じくらい深い意味がある。のかも…