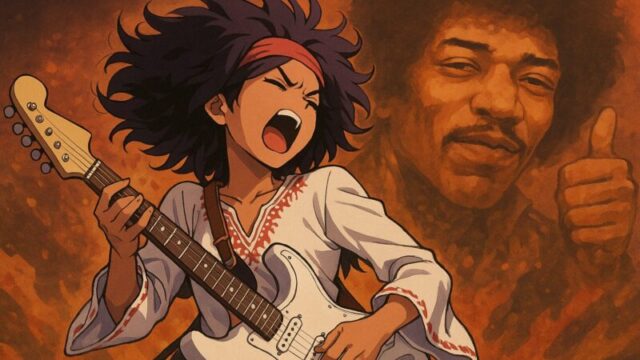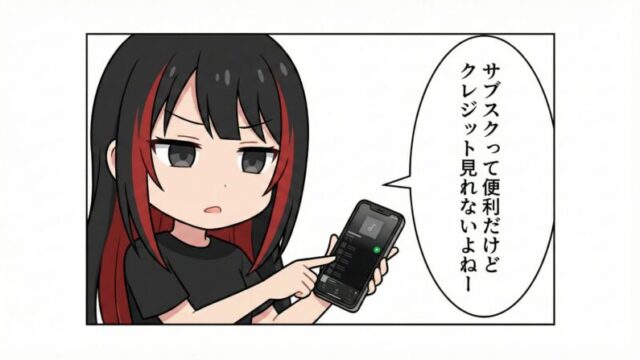バンドマンは“夢を買って赤字を出す”太客である。 そこに希望はあるのか?

ライブハウスに足を運んだことがある人なら、一度はこう思ったことがないだろうか。
「なんか、今日のフロア、妙に静かだな」
でも、それは間違いじゃない。実際、ライブを観ているのは“お客さん”ではなく、その日の対バン──つまり他の出演バンドのメンバーたちだ。
彼らは演者でありながら、同時に“観客”でもある。そしてもう一つ、ライブハウスにとっての最大の“顧客”でもあるのだ。
ライブ1本で赤字●万円の現実
とある無名の4人組バンド、仮に「The Unheard」としよう。
彼らは都内のライブハウスに出演するため、こんな出費を重ねた。
チケットノルマ:30,000円
チケットは1枚1,500円。ノルマは20枚で、合計30,000円。
実際に売れたのは7枚(10,500円分)だったため、19,500円を自腹で支払うことになった。
リハーサルスタジオ代:20,000円
ライブに向けて2時間のリハを5回実施。
スタジオ料金は1時間2,000円で、
2時間 × 5回 × 1部屋 = 合計20,000円
その前の準備として個人でスタジオを借りるメンバーもいる。
特にドラムは自宅練習が困難。習慣的に個人練習のためにスタジオに通っている人が多い。
交通費:19,200円
練習5回とライブ本番の合計6日間
一日あたり800円 × 4人 × 6日分 = 19,200円
正直都内や地方で大分違うと思う、電車なのか車なのか、バスなのか徒歩なのか
今回はざっくり800円で計算してみたが、実際はもっと安く済んでるかも。
反省会(毎回のリハ後の食事):20,000円
「ちょっとメシ行こうか」が恒例に。
この時間がマジで楽しい。
1,000円 × 4人 × 5回 = 20,000円
打ち上げ:14,000円
ライブ当日の夜、居酒屋で乾杯。
その日の出演者、スタッフとの交流の場でもある。
ライブの感想を聞いたり、次回出演の探りを入れたり、ただただ酒が飲みたかったり。
様々な思惑が渦巻く時間だ。
3,500円 × 4人 = 14,000円
もちろん二次会、三次会が発生するケースもある。
合計出費:92,700円
チケット売上:10,500円
実質赤字: 92,700円
メンバー1人あたりの持ち出しは、
23,175円
こんなにかかるの?と思うかもしれないが、これはごく普通のライブ1本分の支出にすぎない。
地方遠征や物販制作、レコーディングとそれに伴うMV撮影などが加われば、出費も収益も変わる。
支えているのは、演者自身だった
「演者は“夢”を提供する側だ」と思っている人は多い。
けれど現実には、夢を見ているのは演者の方なのだ。
ステージに立つには金がかかる。練習するにも金がかかる。
音を届ける手段のすべてに、コストが発生する。
だがそのコストを補填しているのは、ファンでも業界でもない。
演者自身の財布である。
つまりライブハウスも、スタジオも、CDプレス業者も、グッズ印刷会社も、
“売れないバンドマン”たちのおかげで食えている。
演者は、単なる出演者ではない。
ライブハウス経済を回している“スポンサー”であり“最大の太客”なのだ。
それでもライブハウスは儲かっていない
「チケットノルマを取って、ドリンクで儲けて、ライブハウスって実はボロ儲けなんじゃないの?」
──そう思ったあなたのために、ある架空のライブハウス「Keyhall」の数字を元に、ざっくり計算してみよう。

売上構造はこうだ
1日のイベントに5バンドが出演。
各バンドからノルマ(または場所貸し代)として合計150,000円が支払われる。
さらに、観客1人につきドリンクチケット(500円)が1枚売れるとして、
平均的な集客人数を50人と仮定すれば、
ドリンク売上:50人 × 500円 = 25,000円
1日あたりの売上合計:約175,000円
月に20日間稼働した場合:
月間売上:約3,500,000円
一見それなりに見えるが、ここから固定費がのしかかってくる。
支出構造を見てみよう
水道光熱費:約1,000,000円
人件費(スタッフ6人):約1,200,000円
ドリンク原価:100,000円
家賃:500,000円
広告費・雑費:100,000円
支出合計:約3,000,000円
つまりこうだ。
演者からのノルマ・箱貸し:月3,000,000円
観客からのドリンク代:月500,000円
この構造を冷静に見てわかるのは、
ライブハウスの経営は、ほぼ演者からの支払いで成り立っているということ。
観客のドリンク代は、ほとんどそのまま利益になるか、場合によってはそれすらも赤字を埋めるために消えていく。
結局、“お客さん”は誰なのか?
この数字から見えてくるのは、ライブハウスにとっての「客」とは、
足を運んできたファンではなく、“出演料を払ってくれる演者”であるという事実。
ライブハウスのスタッフもまた、演者に依存している。
演者がいなければ、収益は立たない。
でも、演者もまたファンがいなければ続けられない。
これは、誰もが限界ギリギリで支え合っている脆いエコシステムだ。
それでも、誰も声を上げず、ただ「こういうものだ」と思考を止めてしまっている。
無自覚な“搾取”と思考停止の連鎖
一番の問題は、“この状況を疑わないこと”だ。
「出続ければ何かが起きる」
「箱に顔を売っておけばいつかは…」
「とにかくライブは定期的にやった方がいい」
こうした考えは、確かに一理ある。
でも、考えずに出続けることは“戦略”ではなく“消耗”でしかない。
ライブ1本にいくらかかっているのか?
そのコストに見合ったリターンがあるのか?
ファンとの接点は本当にライブハウスだけなのか?
それを考えずに動き続けた結果、何も残らず、貯金だけが消えていく。
夢を叶えるはずのステージが、ゆっくりと自分の心をすり減らす場所になってしまうのだ。
では、どうする?生存戦略としてのライブ活動
誤解しないでほしい。
ライブをやるな、とは言わない。
ただ、スパンを見直して戦略的に出ようという話だ。
たとえば4ヶ月に1回にして、そのぶんSNSでの発信やファンとの接点を強化する。
ライブ以外にも、配信や地域イベントなど“お金をかけずに人に届く手段”は増えている。
音源制作だって、今は自宅でできる。
実際、ビリー・アイリッシュは兄のベッドルームで作った曲でグラミーを獲った。
無名には無名なりの戦い方がある。
選び、考え、工夫すること。
それが今の時代のバンド活動に求められる力だ。
ライブハウスに問われる“集客力”
現在のライブハウスの集客構造は、「出演者=客を呼ぶ存在」という前提の上に成り立っている。
出演バンドがノルマを課されるのは、その日の最低限の収益ラインを保証するため。
それを超える収益は、バンドが何人呼べるかにかかっている。
当然、動員力のあるバンドは大事にされる。
チケットノルマを免除されたり、バックの取り分が優遇されたりする。
一方で、ノルマ未達のバンドは、その分を自腹で補填する。
すると、結果的に“客を呼べないバンドの方が多く払っている”という逆転現象が起こる。
同じパイを食い合う構造
さらに厄介なのは、ライブハウスに足繁く通うリスナーの多くが“複数のバンドの顧客”になっているということ。
つまり、限られた観客数の中で出演者同士が“動員の取り合い”をしているのが実情だ。
こうなると、ライブハウスの中だけでは観客の絶対数が増えていかない。
出演者が増えても、箱もバンドもスケールしていかない。
ではどうするか?
答えはひとつしかない。
ライブハウス自身が“観客の間口”を広げる努力をすることだ。
だが現実には、ブッキングや機材管理、日々のイベント対応で手一杯なライブハウスが多い。
「それ以上のことなんて考える余裕ないよ…」というのが本音だろう。
でも、やらなければならない。
なぜなら、出演者側が“持続可能なペース”で活動するようになったとき、出演頻度が確実に減るからだ。
サステナブルな活動が当たり前になった未来
仮に、すべてのバンドがサステナブルな形態で活動したとしよう。
頻度は下がるが、解散せず、ゆるやかに出演し続けるバンドが増える。
新しい後発バンドも活動しやすくなる。
ライブハウスにとっても“安定した演者層”が育つ土台になる。
だがそれは、あくまで経済的に安定するという話に過ぎない。
ライフステージの変化、モチベーションの低下、人間関係のこじれ──
バンドが解散や活動休止に至る理由は、数えきれないほどある。
つまり、出演者に依存した構造は、もはや限界が近い。
コンテンツの多様化が、未来を救う
今こそ、ライブハウスは「音楽だけの場所」から脱却するタイミングかもしれない。
例えば:
有名配信者によるライブゲーム実況
地元の格ゲー大会やカードゲームイベント
バンドとVTuberのコラボイベント
ライブビューイング上映会
ベンチャー企業のピッチイベント
地元高校生の文化発表の場
音響設備とフロア、照明というライブハウスの強みは、“非音楽イベント”にも通用するポテンシャルを持っている。
それによって多様な客層を取り込み、無名バンドにも立てる舞台を残していくことが、
ライブハウスが今後も文化の発信地であり続けるための条件になるだろう。
夢を見てもいい。でも、目を覚まして動け。
あなたが今ステージに立っているなら、もう一度考えてほしい。
そのライブは、どんな価値を生み出しているか?
その出費は、未来への投資になっているか?
夢を見ることは素晴らしい。だけど、思考停止で“夢を買い続ける”ことは危険だ。
気づかぬうちに、あなたは誰かのビジネスの“上客”になっているかもしれない。
それでも音楽を続けたいなら。
考えよう。選ぼう。行動しよう。
今は、無名にとって最高の時代だ。
使えるものはすべて使って、あなたの音を、あなた自身の手で届けていこう。