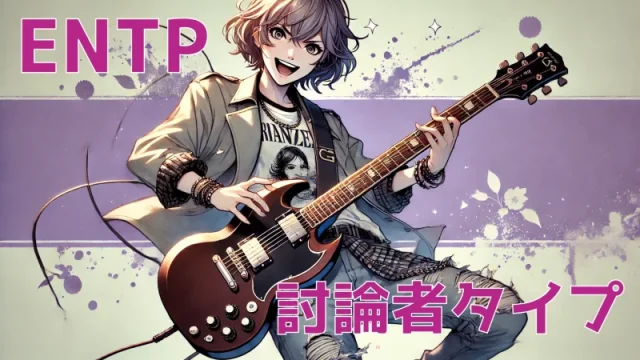ギターでアドリブが弾けるようになるには?譜面からの脱却と実践トレーニング法
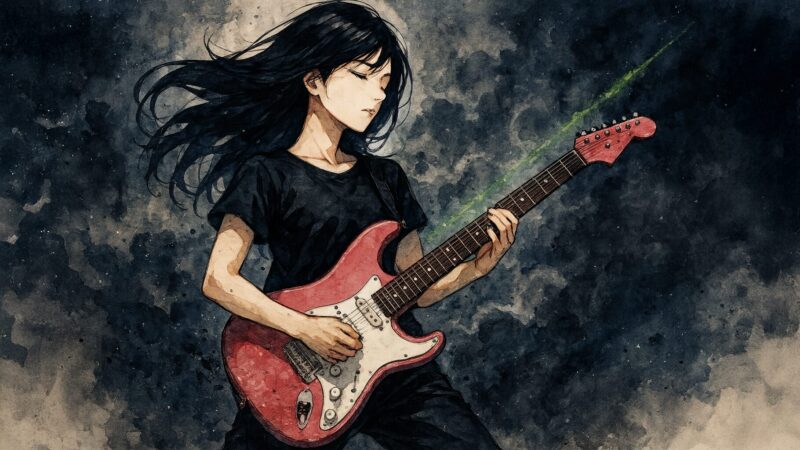
ギターがある程度弾けるようになってくると、次のステップとして多くの人がぶつかるのが「アドリブが弾けない」という壁。
「好きな曲はコピーできるけど、即興でフレーズを作るのは難しい」
「バッキングトラックに合わせて弾こうとしても、何をどう弾けばいいか分からない」
そんなふうに感じたことがある人は少なくないはずだ。
でも、これはあなただけの悩みではない。
むしろ、ほとんどのギタリストが経験する“自然な行き詰まり”でもある。
そしてこの壁を超えるには、単にスケールや理論を覚えるだけでは不十分だ。
本当に必要なのは、譜面という「台本」を手放して、“その場で音楽的に会話する力”を養うこと。
この記事では、ギターでアドリブが弾けるようになるための考え方と、実践的なトレーニング方法を具体的に紹介していく。
アドリブとは「音の会話」——台本なしで表現する技術
アドリブとは即興演奏のこと。だが、それは「テキトーに弾くこと」ではない。
考えてみてほしい。
普段の会話で、台本を見ながら喋る人はいない。
相手の反応や空気を読み、自分の感情や考えをその場で言葉にしていく。
アドリブ演奏とは、まさにそれと同じ。
「音で喋る」「フレーズで会話する」という力が求められるのだ。
ここで大事なのは、「思いついた音を、ラグなくギターで表現する」という能力。
そしてこれは、自然に身につくものではなく、訓練によって伸ばすことができる。
まずは譜面を手放して「自分の音」と向き合う
ギターの練習といえば、TAB譜や動画を見ながら曲を覚えることが一般的だ。
もちろんそれも大切な学習法だが、ことアドリブにおいては“丸暗記”では限界がある。
なぜなら、譜面は“誰かの考えた音”であって、自分の内側から出てきた音ではないからだ。
会話に例えるなら、誰かのセリフを棒読みしているような状態。
アドリブを本当に身につけるには、一度その譜面から離れて、自分の感覚で音を出すトレーニングが必要になる。
では、どんな練習が有効なのか。
ここからは、実際に筆者も実践して効果を感じた具体的な練習法を4つ紹介する。
アドリブ力を伸ばす4つの実践トレーニング
① スケールを「歌いながら」弾く|音感と指板の一致を狙う
たとえばCメジャースケール(ドレミファソラシド)を弾くときに、ギターと同じ音を同時に「歌う」。
これは、「自分の声=内なる音」と「ギターの音」を一致させる訓練だ。
最初は音程がズレても問題ない。
むしろズレに気づけるようになることが目的だ。
この練習により、「音を聴いて位置が分かる」「位置を見て音が浮かぶ」という双方向の音感が養われていく。
ポイント:
弾くポジションはどこでもOK(ローポジでもハイポジでも)
ハミングでも可
一音ずつ丁寧に
この練習は耳と指板の距離を縮める、アドリブにおける最初の土台作りになる。
② 短いフレーズを歌って再現する|「聴いて弾く」力の強化
次に、1〜2小節の短い好きなリックを「歌う→弾く」の順で再現する。
これは「イメージした音を弾く」能力を鍛える練習だ。
ポイント:
歌ってからすぐに弾く
間違えても気にせず繰り返す
弾きながら同時に歌えるようになるとさらに効果的
慣れてきたら同じフレーズを別のポジション、別のキーで弾いてみる。
これは“フレーズの使い回し力”にも繋がる。
まるで同じ単語を違う文脈で使い回すようなイメージだ。
③ バッキングトラックで歌う練習|音楽的な感覚を身体に染み込ませる
YouTubeで「Em バッキングトラック」「ブルース バッキングトラック」などと検索すると、様々な音源が見つかる。
それを流しながらギターを持たずに歌う。
今まで練習したスケールやフレーズをベースに、好きなようにメロディをつけてみる。
ポイント:
最初はEm一発などのシンプルな進行がおすすめ
無理に歌詞をつけなくてもOK。ハミングで十分
フレーズの始まりと終わりを意識する
これによって、「トラックのノリに合わせてフレーズを生み出す」感覚が磨かれる。
アドリブとは「演奏」でもあり「会話」でもあり「ダンス」でもあるのだ。
④ バッキングトラックに合わせて“弾いてみる”|実戦トライ&エラー
いよいよギターを手に取って、③のようなバッキングに合わせて弾いてみる。
できれば「歌いながら弾く」ことを意識したいが、難しければまずは弾くだけでもOK。
ここでは「正しい音」よりも、「流れの中で音を選ぶ」ことが重要だ。
ポイント:
スケール内の音を中心に弾いてみる
“呼吸”を意識して間を作る
リズムが乱れても止まらない
外した音を弾いたときこそ、アドリブ上達のチャンス。
「どうすれば自然につなげられるか?」と考え、身体で覚えていくのだ。
アドリブに必要な“語彙力”=フレーズの引き出しをどう増やすか?
即興演奏といっても、完全なゼロから音を生み出しているわけではない。
優れたギタリストは、自分の中にあるフレーズやリックのストックを、必要に応じて引き出している。
つまり、アドリブには「語彙力=フレーズの引き出し」が必要なのだ。
この引き出しはどうやって増やすのか?
答えはシンプル。「コピーあるのみ」。
好きな曲のコピー
YouTubeやTAB譜で気に入ったリックを練習
コピーしたフレーズを別のキーやポジションで反復
この積み重ねが、あなたの語彙力になる。
そして、それらを組み合わせることで“自分の言葉”が形成されていく。
アドリブ力は作曲力や編曲力にもつながる
アドリブができるようになると、以下のような副次的効果も得られる。
メロディが浮かびやすくなる(作曲に強くなる)
コード進行に合った演出ができる(編曲にも応用できる)
セッションでの対応力が上がる
他人の演奏への理解が深まり、アンサンブル力が増す
つまりアドリブ力は「表現力」であり「対応力」であり、「創造力」でもある。
初心者こそ、早い段階からこうした力を育てておくことで、上達スピードが一気に加速する。
アドリブとは、音を通じて“自分らしさ”を伝えること
アドリブは、単に「スケールを使って適当に弾く」ことではない。
思い浮かんだ音をそのまま出す
ノリに合わせて自由に表現する
会話のように音楽をやりとりする
そういった“自分らしさ”が表れる演奏こそが、本物のアドリブだ。
そのためには、
譜面を手放す勇気
スケールを歌いながら弾く練習
自分の声でフレーズを生み出すトレーニング
コピーによる語彙力の補強
といった習慣が必要になる。
焦る必要はない。少しずつ、自分の音を見つけていこう。
今日の練習から、1フレーズでもいい。
“自分の音”で喋ってみてほしい。
アドリブが弾けるようになるということは、
音楽との距離が、ぐっと近づいたという証だ。