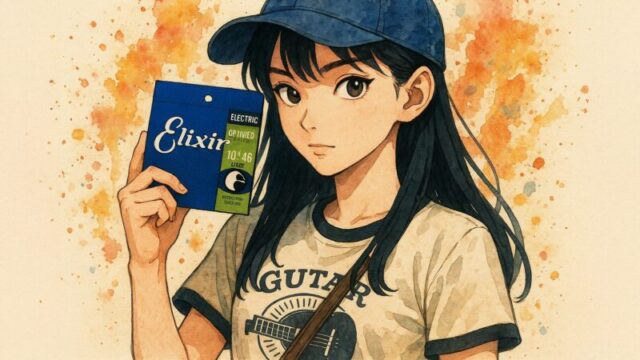「練習してるのに上手くならない…」──
そんな経験はないだろうか?
ギターを始めた当初は、「よし、毎日頑張ろう!」とやる気に満ちていたはずなのに、数週間、数ヶ月と経つうちに、だんだんと気持ちが続かなくなってしまう。
Fコードの壁にぶつかったり、好きな曲が全然弾けなかったり…。そのたびに「自分には才能がないのかも」「もう無理かも」と思ってしまうこと、あると思う。
でもちょっと待ってほしい。
実は、ギターの上達に必要なのは「努力」や「センス」だけではない。
──もっと根っこの部分、「好奇心」が大きな鍵を握っているのだ。
この記事では、ギター初心者や伸び悩んでいる人に向けて、「好奇心」がなぜギターの上達に直結するのか、どんなふうに活かせるのかを解説する。
「やる気」は当てにならない。でも「好奇心」は続く
ギターに限らず、何かを始めたときに最初に生まれるエネルギーは「やる気」だろう。
新しいギターを買ったとき、好きな曲に出会ったとき、YouTubeでうまい人を見て刺激を受けたとき──。
確かに、やる気は大きな力になる。
だがこの「やる気」は、非常に不安定な感情でもある。
思い出してほしい。やる気は何かの拍子に簡単に消えてしまう。
疲れている日
忙しい日
成果が感じられない日
他人と比べて落ち込んだ日
こういった場面では、いくら「やる気を出そう!」と思っても、思うように動けないものだ。
一方、「好奇心」は違う。
✅ 好奇心は、燃え尽きない“探究心”
「どうしてこのコードは気持ちいいのか?」「あの機材はどんな音が出るんだろう?」「この人の右手の動き、なんでこんなにスムーズなの?」──
こういった「なぜ?」「もっと知りたい!」という気持ちは、意識しなくても自然と生まれてくる。
そしてこの好奇心こそ、ギターを長く、そして深く続けていくために最も大切なエネルギー源になる。
【心理学的視点】好奇心がギター上達にもたらすメリット
心理学や脳科学では、好奇心が私たちの学習・創造性・人間関係・自己理解にまで強い影響を与えることが明らかになっている。
それをギターの文脈に置き換えると、次のような効果が期待できる。
① 苦手や偏見を減らしてくれる
「速弾きは自分には無理」「理論はつまらない」といった“思い込み”を取っ払ってくれるのが好奇心だ。なぜ苦手と感じるのか?どうすれば克服できるのか?と前向きに考える視点が身につく。
② 不安や挫折に強くなる
「コードが押さえられない」→「この指の形ってどうすれば楽に抑えられるか」と考えられれば、ただの苦痛が“実験のチャンス”に変わる。
③ 不確実性を楽しめる
今の自分では弾けない曲がある。それでも「分からない」ことにワクワクできると、ゴールの見えない道のりすら楽しめるようになる。
④ 人との繋がりが深まる
「この人の音、どうやって出してるの?」「どんな練習してるんだろう?」と他人に関心を持つことで、バンド活動やSNSでも自然と交流が生まれる。
⑤ 深く考える力がつく
「このフレーズの裏にある理論って何?」といった探求心が、演奏の理解力を高める。理屈から感性へ、逆もまた然り。
⑥ 創造性・協調性が伸びる
「こうしたら面白いかも」とアレンジしてみたり、他人と合わせるときに自分の音がどう機能するかを考えられるようになる。
⑦ 意見の違いを受け入れられる
違うジャンル、違うスタイルのギタリストにも「それもアリ」と思える広い視野が養われる。
⑧ 困難を前向きに乗り越えられる
「今の自分じゃ無理。でもなんで出来ないんだろう?やってみたいな」と思えるマインドが、継続と挑戦のベースになる。
⑨ 自己理解が深まる
「なぜ自分はギターをやってるんだろう?」と問い続けることで、自分のモチベーションの源泉に気づける。
好奇心には“3つの方向性”がある
ギターに限らず、好奇心には次のような3つのベクトルがあると言われている。
1. 内向きの好奇心(自分自身への興味)
どんなプレイが好きか?
なぜ挫折しそうになったのか?
弾いていて気持ちいいと思った瞬間は?
自分の感情や思考に対して「なぜ?」を向けることで、自分に合った練習方法や楽しみ方が見えてくる。
2. 外向きの好奇心(人・社会・他者への興味)
他人のボードの中身が気になる
SNSで上手い人のプレイを分析したくなる
ギターショップで「これ何の木材ですか?」と聞いてしまう
こうした関心が、ギターの幅を広げてくれる。
3. 超越的な好奇心(哲学・宇宙・意味に対する興味)
音楽ってなんで人を感動させるんだろう?
ギターで何を表現したいのか?
自分にとって音楽とは何か?
時には、こうした“抽象的な問い”が、音楽活動に強烈な軸を与えてくれる。
【実践編】好奇心を活かしたギター練習のヒント
以下に、日々の練習に好奇心を取り入れるための具体例を紹介する。
● メトロノームを「遊び道具」に変える
テンポを半分にして、2拍目・4拍目だけに打点を鳴らす練習をしてみよう。拍の裏にグルーヴを感じられるようになれば、リズム感が劇的に向上する。
● 機材の裏側を“知りたくなる”
歪みエフェクターの中でも、「OD-3」と「SD-1」の違いは?
アナログとデジタルの違いは?
単なる試奏ではなく、調べて比べて「なぜ音が違うのか」に注目してみると、音作りの理解が深まる。
● 曲の「なぜ?」を探す
コピーしている曲の中で、「このフレーズが印象的なのはなぜ?」と分析することで、作曲やアドリブのヒントになる。
● SNSを「燃料源」にする
SNSでうまい人を見て落ち込むのではなく、「あの人の手首の使い方、真似してみよう」と具体的な“好奇心の対象”に変えていこう。
“うまくなりたい”を“もっと知りたい”に変えてみよう
ギターが上手くなる人は、ただ努力しているわけではない。
彼らは、ずっと好奇心を燃やし続けている。
「どうして?」「もっと知りたい」──この感情こそが、最大の上達エンジンだ。
やる気は揮発する。でも、好奇心は持続する。
“練習しなきゃ”ではなく、“なんか気になるから触ってみる”くらいの気持ちでいい。
気づけば毎日ギターを手に取り、気づけばちょっと上達している。
そんな自然なサイクルが、一番強い。
今日の練習に、“ひとつだけ”でいい。
「なぜ?」と思えるポイントを探してみてほしい。